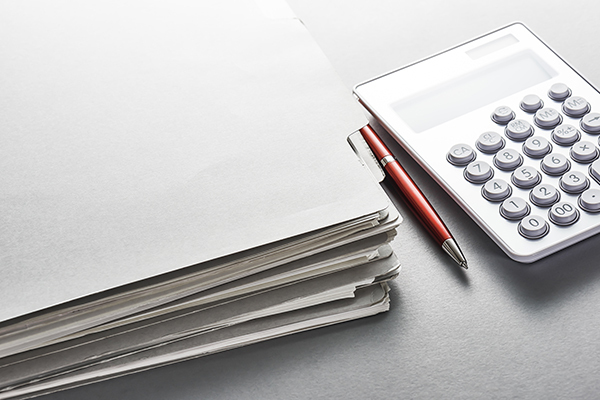中小企業における資金繰り予測の必要性 —— 税理士の視点から見る経営のリアル
中小企業経営において、資金繰りは最重要課題の一つです。利益が出ていても、資金が足りなければ会社は回りません。逆に、資金繰りが安定していれば、一時的な赤字も乗り切れます。それほどまでに「お金の出入り」の管理は、企業の命綱とも言えます。
税理士として多くの中小企業と接してきた立場から断言できるのは、「資金繰り予測を行っている企業は、圧倒的に経営が安定している」という事実です。本稿では、資金繰り予測の重要性、具体的に何をどのように予測すべきかについて掘り下げていきます。
なぜ「資金繰り予測」が必要なのか
1. 利益と資金は別物
まず経営者が理解すべきは、「利益が出ている=お金が増えている」ではないということです。たとえば、売上が計上されても、入金は2ヶ月後。仕入は現金払い。こうしたタイムラグが生むのが、資金繰りのギャップです。
実際、黒字倒産の多くは、このギャップに起因しています。PL(損益計算書)だけを見て経営判断をしていると、ある日突然資金が底をつき、慌てて借り入れを申し込むも間に合わず……という事態に陥りかねません。
2. 銀行対応の必須ツール
資金繰り予測は、金融機関との信頼関係構築にも欠かせません。銀行は融資先の「将来の返済可能性」を見ています。利益計画よりも、現金収支の予測の方が、融資判断においてはるかに重要です。
適切な資金繰り予測をもとに、「この時期にいくらの運転資金が必要で、どのように返済していくか」が明確に説明できれば、金融機関の信頼は格段に上がります。逆に、計画のない資金調達は「場当たり的」と判断され、融資に悪影響を及ぼします。
税理士が見る「予測すべき資金項目」
資金繰り予測は、単なる一覧表ではなく、「戦略的ツール」です。税理士の立場から、以下の要素を網羅する予測が望ましいと考えます。
1. 入金予測
-
売掛金の回収予定(得意先ごと、支払サイトごと)
-
現金売上の動向(季節変動も含め)
-
雑収入や補助金・助成金の入金予定
ここで重要なのは「確度別に分類する」こと。確定、ほぼ確実、不確定、といったランク付けにより、楽観的な見積もりに偏ることを防ぎます。
2. 出金予測
-
仕入・外注費の支払予定
-
給与、賞与、社会保険料の支払時期と金額
-
税金(消費税、法人税、事業税など)の納付時期
-
借入金の返済スケジュール
-
家賃、水道光熱費、通信費などの固定費
特に税金は忘れがちです。決算時に「思っていたより税金が高い」と資金不足になる例が後を絶ちません。
3. 借入・返済予定
-
新規融資の着金時期
-
返済額の減額・増額予定(リスケ、借換含む)
資金繰り予測には、これらの金融取引も必ず反映すべきです。借入・返済の流れを織り込むことで、資金残高の変動にリアリティが出ます。
資金繰り予測を導入するメリット
1. 早めの対応ができる
資金ショートの「兆候」を1〜3ヶ月前に発見できれば、打つ手は増えます。銀行への借入相談、回収条件の見直し、支払の先延ばし交渉、など対応策は複数あります。事前に気付けば打てる一手が、気付かなければ「資金ショート→倒産」の一本道です。
2. 経営判断がブレなくなる
設備投資や人員増加、新規出店など、大きな経営判断には「手元資金の見通し」が不可欠です。資金繰り予測があることで、「今やるべきか否か」の判断に説得力が生まれます。
3. 税理士との連携が深まる
税理士が数字の読み解きをサポートすることで、経営者は数字に強くなります。月次の予測と実績の差異分析を行うことで、「何が想定と違ったのか」「次はどう修正すべきか」を議論できるようになります。
まとめ:資金繰り予測は「攻め」の経営戦略
資金繰り予測は、「防御」の手段ではなく、「攻め」のツールです。未来の資金の流れを見える化し、余裕があるときに打ち手を考える。そうすることで、資金に振り回されない経営が可能になります。
税理士を単なる税務申告代行者ではなく、「経営の伴走者」として活用し、資金繰り予測を通じて企業の倒産リスクを未然に防ぎ、持続的な成長に役立ててください。