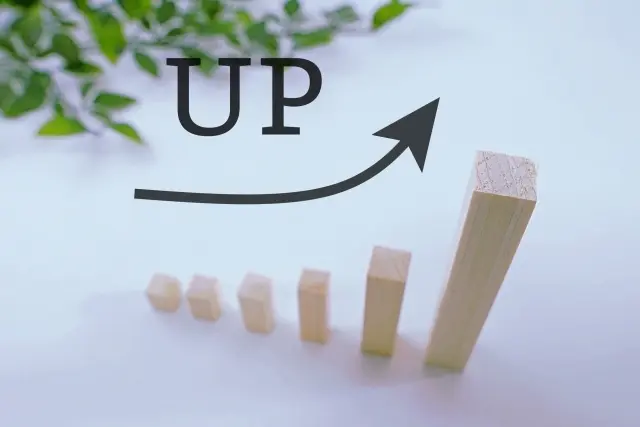ブログ記事一覧
-

決算前の駆け込み出費、それ本当に「節税」ですか? 税理士が見てきた「お金が消える会社」の共通点
「税金を払うくらいなら、何か買ってしまおう」という発想の落とし穴 決算が近づくと、こんな会話が社内で交わされることはありませんか。 「このままだと利益が出すぎてしまう。税金で持っていかれるくらいなら、今のうちに何か経費で使ってしまおうか」 ... -

忙しいのに儲からない社長と、余裕があるのに稼ぐ社長の決定的な違い
毎日やることに追われて、気づけば夜。朝から晩まで働いているのに、売上にはつながっていない気がする…。そんなモヤモヤを抱えていませんか。 実は、私も起業したばかりの頃は同じ悩みを抱えていました。メールを返して、名刺を整理して、資料を作り込ん... -

明日、主力事業が消えたら?中小企業社長が知っておくべき多角化戦略
はじめに:なぜ事業の柱は3本必要なのか 経営者として日々奮闘しているあなたに、ひとつ質問があります。 今のビジネス、柱は何本ありますか。 もし1本だけだとしたら、少し立ち止まって考えてみてください。1本足や2本足のイスがグラグラ揺れるように、事... -

なぜ、新規開拓に必死なのに売上が安定しないのか? 経営者が見落としがちな「売上の方程式」の正しい使い方
はじめに ── あなたのビジネスに羅針盤はありますか? 日々の業務に追われていると、つい目の前の仕事をこなすことだけで精一杯になってしまいます。新規のお客様を増やさなければ、売上を伸ばさなければ。そんな焦りを感じている経営者の方も多いのではな... -

なぜあの会社は少ない労力で稼げるのか?高収益ビジネスに共通する3つの仕組み
はじめに:毎月の売上に一喜一憂していませんか 商品が売れた月は安心できるけれど、翌月はまたゼロからのスタート。 こんな状況に心当たりはありませんか。 中小企業を経営していると、どうしても目の前の売上を追いかけることに精一杯になりがちです。新... -

3割引きしたら販売数1.75倍でやっと同じ利益、それでも値下げを続けますか?
売上が伸び悩むと、つい値下げに手を伸ばしたくなるものです。価格を下げれば顧客が増えて、結果的に利益も増えるはず。そう考えるのは自然なことかもしれません。競合他社が値下げを仕掛けてくれば、対抗せざるを得ないという焦りもあるでしょう。 しかし... -

「売上は増えたのに利益が残らない」その原因、商品の届け方にありました
売上が伸びれば、利益も自然についてくる。多くの経営者がそう考えています。でも、本当にそうでしょうか。 実は、商品やサービスをどうやってお客様に届けるか、つまりデリバリーの方法によって、利益率は大きく変わってきます。同じ商品を売っていても、... -

あなたの会社は何を売っていますか?中小企業の命運を分ける4つの商品モデル
はじめに|売り方より先に考えるべきこと 「もっと営業力を上げなければ」「広告を増やせば売れるはず」そう考えて販売手法ばかりに目を向けていませんか。 もちろん、売り方を磨くことは大切です。しかし、どれだけ優れた営業トークを身につけても、どれ... -

起業初期の不安を乗り越える、あなたに合ったお客様は必ずいます
はじめに これから独立を考えている方、あるいは起業したばかりの方にとって、最初にぶつかる壁は何でしょうか。多くの場合、それは「最初のお客様をどうやって見つけるか」という問題ではないでしょうか。 私も開業当初は夜も眠れないくらいに悩みました... -

売上を追いかけても楽にならない理由。経営者が知るべきビジネスモデルの基本設計
はじめに:ビジネスモデルとは、結局何なのか 日々の経営に追われていると、ふと「うちのビジネスモデルって、これでいいんだろうか」と考える瞬間はありませんか? 「ビジネスモデル」という言葉はよく耳にしますよね。会議や書籍、ビジネス系のメディア...