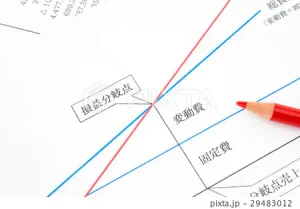「ウィッシュ」に寄り添えば、利益も節税も変わる

こんにちは。越谷市の法人税務を専門とする税理士の若尾です。
今回は、少し違った角度から「お金が残る経営」についてお話します。
多くの経営者が、売上を伸ばすために「何が欲しいですか?」「どういうサービスが必要ですか?」と、お客様のウォンツ(Wants)やニーズ(Needs)に応えようとします。もちろん、これは間違いではありません。
でも、それだけでは利益は安定せず、節税の余地も生まれにくいのが現実です。
理由は簡単で、「表面的な要望に応えるだけでは、取引の深さ(=利益率や継続性)が生まれにくい」からです。
そこで、今回はウォンツやニーズの先にあるお客様のウィッシュ(Wish)を満たし、深い取引関係をつくり、高い利益率と節税を実現する方法についてご紹介します。
「ウォンツ」と「ウィッシュ」は別物
お客様の「ウォンツ」とは、表面的な欲求です。たとえば「名刺が欲しい」「ホームページを作りたい」といったもの。
その言葉の通り「欲しい」です。
このウォンツを満たす段階で勝負すると、競合との比較が避けられず、「誰が一番安いか」「どこが早いか」で選ばれることとなります。
価格競争やスピード勝負になりやすいので、利益率も下がります。
一方で、「ウィッシュ」とは、その奥にある本当の「願い」です。
たとえば、
- 名刺を作りたい → 実は「自信を持って営業したい」
- ホームページを作りたい → 実は「採用に苦戦していて、会社の魅力を伝えたい」
このように、ウォンツの奥には「どうなりたいか」という願いが必ず存在しています。
この「ウィッシュ」に気づき、それに寄り添った提案や商品設計ができると、単価が上がり、継続性が生まれ、競合との比較から抜け出すことができます。
つまり、「価格」や「スペック」ではなく、「共感」や「信頼」で選ばれるようになるのです。
「ウィッシュ」に寄り添うと、なぜ利益が残るのか?
その理由はシンプルです。ウィッシュに寄り添った提案は、顧客にとって「代替不可能」な価値になります。
欲しいと言ったものを機械的に提案されるのであれば、判断基準は価格となります。
自分のことを真剣に考えてくれる人、自分のことをわかってくれている人から提案されれば、あなたから買いたいとなります。
結果として、
- 顧客との関係性が深まり、値下げされない
- 必要性ではなく「共感」で選ばれるため、乗り換えられにくい
- 本音の会話が増えることで、時系列リピート(次の取引)を設計しやすい
- 顧客の期待を上回る提案ができるため、信頼が厚くなり紹介も生まれる
つまりは、
「ウィッシュ」を起点にした商品・サービスは、利益率も継続率も高くなる
ということです。
さらに、このような取引が増えると、営業活動が効率化され、無駄なマーケティングコストが減っていきます。広告費や営業人件費が軽くなることで、利益はより安定して残るようになります。
これは、いわば信頼資産によって回るビジネスです。信頼は一度築ければ長く続き、価格競争に巻き込まれずに取引が成立するようになります。
なぜ「ウィッシュ」に寄り添うと、節税にもつながるのか?
一見、ここまでご紹介してきた信頼ベースの取引の話と節税は関係なさそうに思えますが、実は大きく関係しています。
顧客の「ウィッシュ」に寄り添って得た収益は、
- 継続性があり見込みが立ちやすい(ということは「節税計画を立てやすい」)
- 単価が高いため、同じ売上でも利益率が高くなる(ということは「節税の余力ができる」)
これらは、節税対策を行う際に大きな意味を持ちます。
利益の見込みが立つため期初から節税対策を仕掛けられます。利益率が高いため使える経費も多くなります。
決算間際で慌てて使った経費と期初から計画的に使った経費では、どちらが将来の利益を生むかは明白です。
節税の定義は、経費を使って税金を減らすことではありません。
「効果的に経費を使って税金を減らし、将来の利益につなげること」です。
そのために、継続性があり、利益率が高い、ウィッシュにもとづく収益が最適なのです。
お客様の「ウィッシュ」を見つける質問とは?
では、どうすれば「ウィッシュ」を見つけられるのか?
鍵は、お客様の問いに対してすぐに答えず、「どうしてそう思われたんですか?」と一歩掘り下げることです。
この「なぜ?」の問いによって、お客様はウォンツの先のウィッシュを話し始めます。
たとえば、
「ホームページを作りたいんです」(ここですぐにサービスの紹介へ移行しない)
→「どうしてそう思われたんですか?」
→「実は、採用がうまくいってなくて、ホームページで会社の魅力を伝えたいんです」
ここまで来れば、提案するサービスの軸が大きく変わってきます。
単なるWEB制作物ではなく、「採用ブランディングのためのWEB戦略」に変わり、金額も納期も変わってきます。
このような提案ができると、お客様は「この人は自分の本音を理解してくれている」と感じ、価格よりも信頼で選んでくれるようになります。
この一問の差が、会社の利益構造すら変えてしまうほど、大きな意味を持っています。
まとめ:「どうしたいか?」に寄り添うと、利益が残る
お客様が「何を欲しいか」ではなく、「どうなりたいか」に寄り添う。
このシフトができると、
- 他社と競争しなくてよくなる
- 営業や価格交渉のストレスが減る
- 単価が上がり、継続率も上がる
- 結果として、キャッシュが残る
- そして、節税の幅が広がる
という好循環が生まれます。
お金が増える経営体質をつくるためには、まずは「お客様のウィッシュに寄り添う設計」ができているか?
これを考え抜くことが、利益と節税、どちらにも効く本質的な経営改善になります。
売上が伸び悩んでいる、キャッシュが残らない、節税がうまく機能していない。
そんな時こそ、目の前のお客様の「欲しい」の奥にある「本当の願い」まで掘り下げてみてください。
その願いに応える設計こそが、経営改善の鍵です。