「節税しすぎて銀行評価が下がる」罠から抜け出すには
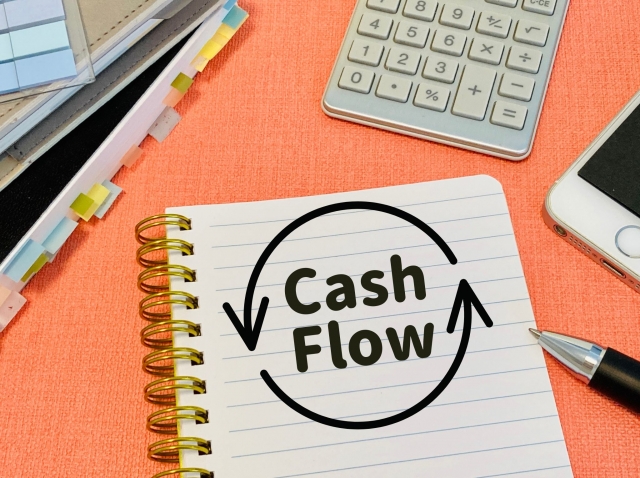
はじめに:節税を頑張るほど、なぜかお金が借りにくくなる?
「税金はできるだけ払いたくない」
これは、経営者であれば誰もが一度は思うことではないでしょうか。
利益が出れば出るほど税金も増えていく。
それなら、経費をうまく使って利益を抑え、税金を減らしたい。
そう考えるのは、ごく自然な感覚です。
ところが、この節税したいという気持ちが強くなりすぎると、思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあります。
それが、銀行からの評価が下がるという問題です。
節税を頑張っているのに、なぜか融資の条件が厳しくなった
銀行の担当者の態度が、以前より冷たくなった気がする
もしこんな経験があるなら、それは偶然ではないかもしれません。
実は、節税と銀行評価の間には、多くの経営者が見落としがちなトレードオフの関係があるのです。
今回は、この節税しすぎて銀行評価が下がるという罠の正体と、そこから抜け出すための考え方についてお伝えしていきます。
銀行が見ているのは税金の少なさではなく返済能力
まず押さえておきたいのは、銀行がどんな視点で会社を評価しているか、ということです。
銀行は、融資先の企業を債務者区分というランクで分類しています。この区分は、金融庁の監督指針に基づいて行われるもので、融資条件に大きな影響を与えます。
金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」によると、この債務者区分を判断する際の重要な基準として、「実質的な債務超過の状態にあるかどうか」「経常損失(赤字)が続いているかどうか」が挙げられています。
具体的には、業況が良好で財務内容にも問題がない企業は「正常先」として分類されます。
一方、業況が低調で実質債務超過の状態にある、あるいは赤字が続いているなど返済能力に問題がある企業は「要注意先」以下に分類されてしまうのです。
つまり、節税のために利益をギリギリまで削り、赤字すれすれの状態を続けていると、銀行の内部では「正常先」から「要注意先」へとランクダウンしてしまう可能性があるということです。
ランクが下がれば、当然ながら融資の審査は厳しくなります。希望する金額を借りられなくなったり、金利が高く設定されたりすることも珍しくありません。
内部留保が少ない会社は体力がないと見なされる
銀行が重視するもう一つのポイントが内部留保、つまり会社に蓄積された利益です。
この内部留保の多さは、自己資本比率という指標に反映されます。自己資本比率とは、会社の総資産のうち、返済不要な自己資本が占める割合のことです。
中小企業庁の「中小企業白書」の分析によると、自己資本比率が高い企業ほど、金融機関からの借入が容易であると回答する割合が高くなる傾向があります。
また、自己資本比率が低い企業は借入の金利が高くなる傾向も、データとして明確に示されています。
これは感覚的な話ではなく、統計的な事実です。
節税を優先するあまり毎年の利益を限りなくゼロに近づけていると、当然ながら内部留保は増えていきません。
10年経っても20年経っても、自己資本比率は低いままです。
その結果、融資を受けにくくなり、受けられたとしても金利が高くなってしまうのです。
銀行はお金を貸す以上、返してもらえないと困ります。
内部留保が少なく、ちょっとした逆風ですぐに倒れてしまうリスクがある会社に対しては、どうしても慎重にならざるを得ないのです。
銀行が本当に見ているのはキャッシュフロー
銀行が税金を払ってでも利益を残す会社を好む理由は、もう一つあります。それはキャッシュフローという視点です。
金融庁が公表している「金融仲介機能のベンチマーク」などの指針において、金融機関は企業の債務返済能力(キャッシュフロー)を重視すべきとされています。
借入金の返済原資は、一般的に減価償却費と税引後当期純利益の合計で計算されます。これを簡易キャッシュフローと呼びます。
ここで注目していただきたいのは、税引後当期純利益という部分です。
過度な節税によって利益を圧縮すると、この税引後当期純利益も当然小さくなります。
すると、銀行が評価する返済原資(キャッシュフロー)も自動的に減少してしまうのです。
つまり、節税を頑張れば頑張るほど、公的な評価基準における「お金を返す力」を自ら減らしていることになります。これでは、融資審査で不利になるのは当然のことです。
税金ゼロを目指す会社が逃してしまう大きなチャンス
利益を削りすぎてしまうことのデメリットは、融資を受けにくくなることだけではありません。
実は、もっと大きなビジネスチャンスを逃してしまう可能性もあります。
たとえば、大手企業との取引を始めようとするケースを考えてみましょう。
大手企業は、新しい取引先と契約を結ぶ前に、必ずと言っていいほど信用調査を行います。取引先が突然倒産してしまっては困るからです。
この信用調査で見られるのは、やはり利益と内部留保です。
決算書を見て、この会社は安定して利益を出しているか、十分な内部留保があるか、といったことがチェックされます。
もし、節税にこだわりすぎて利益を圧縮し続けていたら、どうなるでしょうか。
大手企業の目には財務基盤が弱い会社として映ってしまいます。「この会社と取引して大丈夫だろうか」「途中で資金繰りに行き詰まって迷惑をかけられないだろうか」と不安に思われてしまうのです。
その結果、せっかくの大きな取引の話が流れてしまうこともあります。
節税で数十万円、数百万円の税金を減らすことには成功したけれど、その代わりに数千万円規模の取引チャンスを失ってしまった。これでは、本末転倒です。
経営者保証を外すためにも利益と内部留保は必要
近年、国は経営者保証(社長個人の連帯保証)を不要とする融資を推進しています。会社の借入に対して社長個人が保証人にならなくてよい、という仕組みです。
これは経営者にとって非常にありがたい制度ですが、誰でも経営者保証を外せるわけではありません。
金融庁と中小企業庁が所管する経営者保証に関するガイドラインでは、保証を外すための要件として、
「財務基盤の強化(利益計上による内部留保の拡充など)が図られていること」
「適時適切な情報開示(決算書等の説明)が行われていること」などが挙げられています。
つまり、しっかり利益を出して内部留保を増やし、銀行に対して決算内容をきちんと説明できる会社でなければ、経営者保証は外せないのです。
節税にこだわるあまり利益を出さない経営を続けていると、いつまで経っても社長個人が借入の保証人から解放されません。
万が一会社が倒産した場合、社長個人の財産まで失ってしまうリスクを抱え続けることになります。
選択肢の多い経営を実現するためには、利益を出して内部留保を増やすことが欠かせません。
本当に目指すべきは税金を払ってもお金が残る状態
では、どのように考えればよいのでしょうか。
結論から言えば、目指すべきは税金をしっかり払って、それでもなお手元に十分なお金が残っている状態です。
目安としては、最低でも月商1ヶ月分の現金を手元に持っておきたいところです。できれば月商2〜3ヶ月分の現金があると、より安心できます。
このレベルの手元資金があれば、銀行からの評価は確実に上がります。
融資を受けやすくなり、金利も有利な条件を引き出せる可能性が高まります。
また、何か良いビジネスチャンスが巡ってきたときに、すぐに投資することができます。予想外のトラブルが起きたときにも慌てずに済みます。
税金を払ってもお金が残る状態を作ることで、経営の選択肢が大きく広がります。
節税と銀行評価を両立させる三つの考え方
ここまでの話を踏まえて、具体的にどのような姿勢で経営に臨めばよいか、三つのポイントにまとめてみます。
一つ目は、赤字ギリギリまで利益を削る節税はやめる、ということです。
営業利益や経常利益は、基本的に黒字をキープしましょう。
先ほどご紹介したように、赤字が続くと銀行の債務者区分で要注意先に分類されてしまう可能性があります。正常先の評価を維持するためにも、黒字経営を続けることが大切です。
二つ目は、お金を生む節税だけを選ぶ、ということです。
将来の売上や利益アップにつながる投資、社員の定着率を高めるための福利厚生の充実、業務効率を上げる設備投資。
こうした支出は、経費として計上できるので税金は減りますが、同時に会社の価値を高めることにもつながります。
一方、単に税金を減らすためだけに必要のないものを買うのは避けましょう。
お金は出ていくのに何のリターンも生まない。これでは会社の体力を消耗するだけです。
三つ目は、銀行とオープンに付き合う、ということです。
決算書ができたら、銀行へ説明に行くことをおすすめします。
これは経営者保証を外すための要件の一つでもある適時適切な情報開示にも該当します。
前期からの変化、今後の見通し、どんな投資を行ったか。
そうしたことを数字に基づいて説明できれば、銀行との信頼関係は確実に深まります。
おわりに:選択肢の多い経営を目指して
節税は決して悪いことではありません。払わなくてよい税金を払う必要はないのです。
しかし、節税にこだわりすぎるあまり、銀行からの信頼を失い、ビジネスチャンスを逃し、会社の体力を削ってしまっては本末転倒です。
しっかり利益を出して、税金も払う。
それでもなお、手元に十分なお金が残っている。
そんな状態を目指すことで、経営の選択肢は大きく広がります。
節税と銀行評価の罠から抜け出して、本当の意味でお金が残る会社を作っていきましょう。










