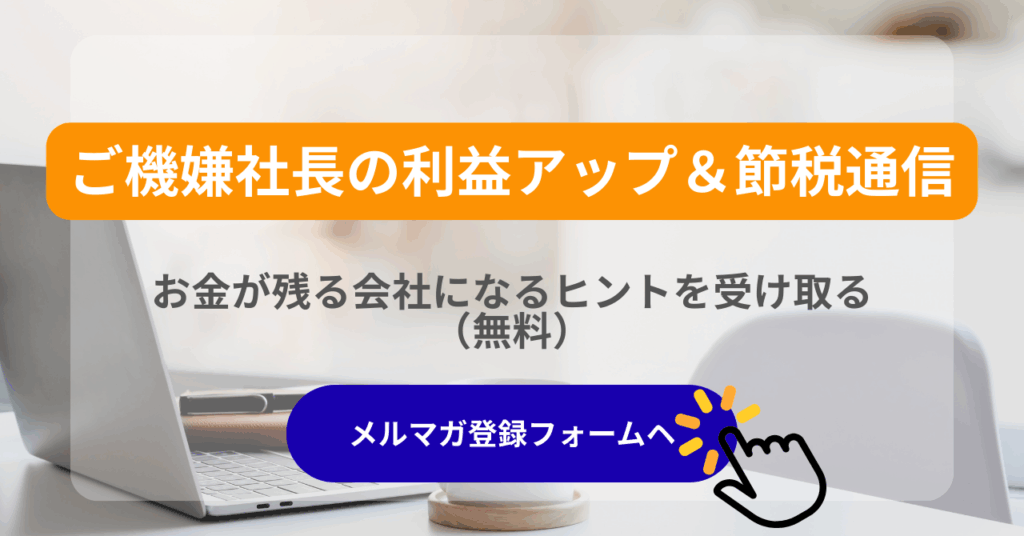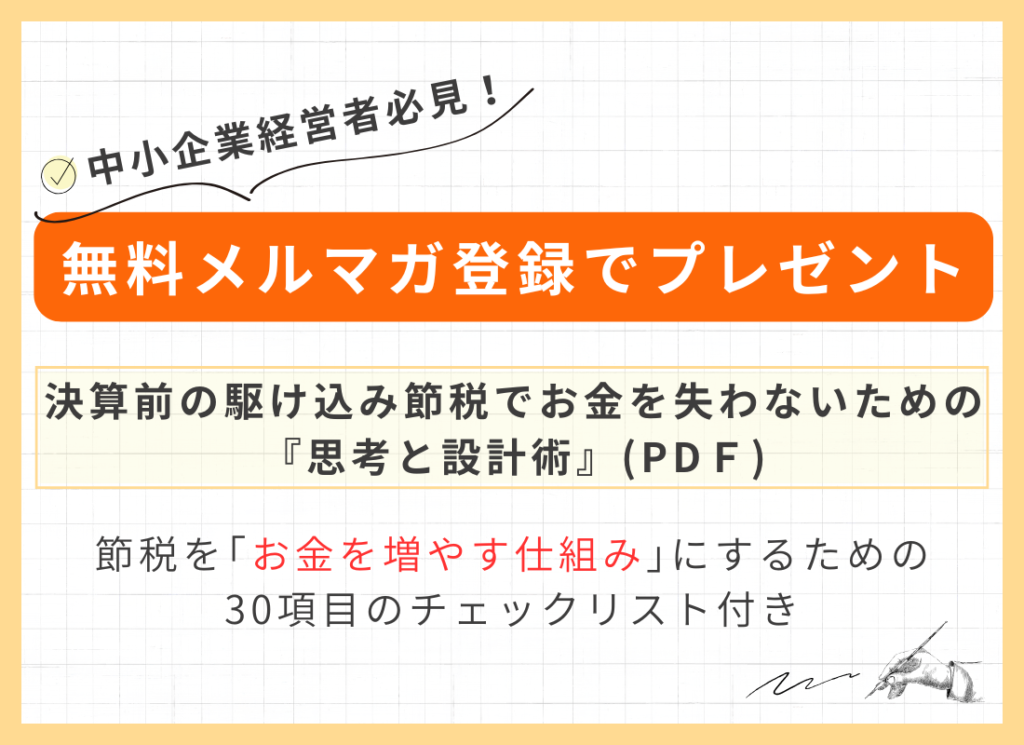「修正申告すれば終わりますよ」税務調査官のやさしい一言で、会社が数百万円損をするかもしれません

税務調査が終わりに近づくと、調査官がこんなふうに声をかけてくることがあります。
「社長、いくつか指摘事項が出ました。修正申告をしていただければ、今回の調査はこれで終わりにできます。お忙しいでしょうから、いかがですか?」
穏やかな口調で、まるで助け船を出してくれているように聞こえるかもしれません。
やっと終わると安心して、つい内容をよく確認しないままハンコを押してしまう社長も少なくありません。
でも、ここで少しだけ立ち止まってみてください。
そのハンコには、想像以上に重い意味があります。
場合によっては、自分が不正をしたと全面的に認めたことになってしまうかもしれません。
もしそうなったら、どうなるか想像できますか?
しかも、一度提出した修正申告は原則として取り消せないため、あとから後悔しても手遅れになります。
この記事では、税務調査で修正申告をすすめられたときに確認すべきポイントと、安易に応じることで発生する重加算税のリスクについて、わかりやすくお伝えしていきます。
修正申告と更正には大きな違いがあります
税務調査で誤りを指摘されたとき、その決着のつけ方には2つの道があります。
ひとつ目は、修正申告です。
これは納税者自身が間違いを認めて、自ら申告書を出し直す方法になります。
調査が早く終わるというメリットがありますが、原則として不服申し立て、つまり裁判で争うことができなくなるという大きなデメリットがあります。
ふたつ目は、更正です。
こちらは納税者が誤りを認めない場合に、税務署長が職権で強制的に処分を行う方法になります。
税務署と対立する可能性がある反面、処分に納得できなければ異議申し立てや裁判で争う権利が残ります。
調査官が修正申告をすすめてくるのは、更正の手続きが事務的に大変だからという側面もあります。
納税者の同意を得て終わらせるほうが、調査官にとっても効率がよいわけです。
ここで大切なのは、指摘された内容に本当に納得しているかどうかという点です。
単なる計算ミスなら修正申告で問題ありません。
しかし、見解の違いがある場合や、重加算税が関わってくる場合は話が変わってきます。
その修正申告に重加算税が含まれていませんか?
調査官から修正申告をすすめられたとき、最も注意すべきポイントがあります。
それは、指摘事項の中に重加算税(税率35%から40%)の対象が含まれているかどうかです。
あなた自身はうっかりミスだと思っているのに、調査官は意図的な隠蔽や仮装だと判断していたらどうでしょうか。
この認識のズレを放置したまま修正申告を出してしまうと、調査官の主張を丸ごと認めたことになりかねません。
そもそも重加算税が課される隠蔽や仮装とは、具体的にどんな行為を指すのでしょうか。
隠蔽(いんぺい)とは、二重帳簿をつけたり、売上を帳簿から外したり、証拠となる書類を捨てたり隠したりする行為を指します。
仮装(かそう)とは、架空の契約書を作ったり、他人の名前を使ったり、請求書や領収書を書き換えたりする行為です。
こうした行為に心当たりがあるなら、重加算税は避けられません。
素直に修正申告に応じるのが現実的な判断になるでしょう。
ただし、調査官との間で解釈の違いが生じている場合は、簡単に応じるべきではありません。
脱税するつもりがなくても重加算税になることがあります
ここで、多くの経営者が見落としがちなポイントをお伝えします。
「脱税するつもりなんてなかったのだから、重加算税にはならないはずだ」
そう思いたい気持ちはよくわかります。
しかし、過去の最高裁判例(昭和62年5月8日判決)は、経営者にとってかなり厳しい判断を示しています。
この判例の趣旨を簡単にまとめると、税金を減らそうという明確な意図がなかったとしても、帳簿を隠す・書類を書き換えるといった行為そのものを故意に行っていれば、重加算税の対象になるということです。
あなたの会社の帳簿や書類は、きちんと管理されていますか?
調査官はまさにこの点を突いてきます。
「社長、この書類は書き換えていますよね。脱税の意図があったかどうかは問題ではありません。書き換えた事実がある以上、重加算税の対象になります」
こういうロジックで迫られたとき、もし本当に書き換えた事実がない場合や、正当な理由がある場合は、決して認めてはいけません。
社員や税理士がやったことでも社長の責任になるのでしょうか
「経理を担当している妻が勝手にやった」
「顧問税理士が独断で処理した」
自分は直接関わっていないのだから、重加算税だけは勘弁してほしいという主張もよく耳にします。
気持ちはわかりますが、残念ながら過去の判例を見る限り、この主張が認められるのはかなり難しいのが現実です。
裁判所は、納税申告を第三者に任せたとしても納税者自身の申告義務はなくならず、その人が行った申告は納税者本人が行ったものとして扱われるべきだという考え方を示しています。
つまり、社長が直接手を下していなくても、監督する立場にある以上、社長自身の行為とみなされて重加算税が課されるケースが多いということです。
ただし、例外もあります。
社長が十分な注意を払っていたにもかかわらず、第三者が勝手に不正を行ったという特別な事情が認められる場合には、争う余地が残されています。
そのような場合は、安易に修正申告せず、事実関係をしっかり整理して臨むことが大切です。
修正申告に応じるべきかどうか、3つのケースで考えてみましょう
ここからは、実際に調査官から修正申告をすすめられたときの判断基準を、3つの場面に分けて整理していきます。
ケースA:明らかに不正があった場合
売上の除外や架空経費の計上が事実であり、調査官にも証拠を押さえられている状況です。
この場合は、修正申告に応じるのが現実的な選択になります。
抵抗しても勝ち目はほとんどありません。
早めに対応して延滞税、つまり利息にあたる部分を少しでも抑えるほうが得策です。
ケースB:見解の相違でグレーゾーンになっている場合
交際費か給与かの判断や、売上の計上時期のズレなどが争点になっているケースです。
調査官は仮装だと主張するけれど、こちらとしては解釈の違いに過ぎないと考えている。
そんな状況で、言われるがまま修正申告を出してしまってよいのでしょうか?
こうした場面では、すぐに修正申告に応じるべきではありません。
重加算税を外してもらえるなら修正申告に応じるという交渉は、実務の現場ではよく行われています。
まずは内容について納得いくまで話し合いを重ねてください。
ケースC:まったく身に覚えがない場合
帳簿を隠しただろうと言われているけれど、実際には紛失しただけ。
改ざんだと指摘されているけれど、正規の手続きで訂正しただけ。
このような状況では、絶対に修正申告に応じてはいけません。
応じてしまうと、やっていない不正を自分で認めたことになり、重加算税まで課されてしまいます。
たとえ更正という形で処分を受けることになっても、不服申し立ての制度を使って身の潔白を証明すべきです。
ハンコを押す前に思い出してほしいこと
税務調査の現場で、調査官がこんなプレッシャーをかけてくることがあります。
「修正申告に応じないと、もっと徹底的に調べることになりますよ」
こうした言葉を聞くと、つい怖くなって応じたくなるかもしれません。
でも、忘れないでください。
修正申告は義務ではなく、あくまでも任意の行為です。
調査官の指摘に少しでも納得できない部分がある場合、とくに重加算税につながる隠蔽や仮装の認定に不服がある場合には、その場で回答する必要はありません。
修正申告書に押すハンコの重みは、会社のこれからの信用に直結しています。
あなたの冷静な判断が、理不尽なペナルティから会社を守ってくれるはずです。