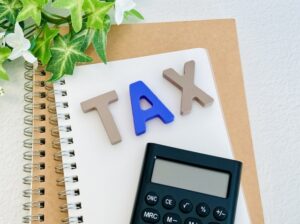シナジー経営と節税―税理士任せからチームでお金を残す会社へ

スティーブン・コヴィー博士の『7つの習慣』をご存知でしょうか。
第6の習慣は「シナジーを創り出す」です。
1+1を2ではなく3にも4にもする、創造的な協力の原則として知られています。
実は、この考え方は節税や会社のお金の話にも、そのまま当てはまります。
節税や資金繰りの話になると、「税理士さんに任せてあるから大丈夫ですよ」とおっしゃる経営者の方が多いのですが、実際のところ、本当にお金を残していくためには税理士だけでは不十分です。
今回は、税理士だけでなく、社労士、金融機関、保険やITの専門家など、さまざまな専門家を巻き込んだシナジー節税という考え方をお伝えしていきます。
いま、企業に求められているのは財務情報だけではありません
2023年3月、経済産業省は「人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書」というものを公表しました。
この報告書では、従業員のスキルやモチベーションといった「人的資本」への投資が企業価値向上につながり、金融機関や投資家からの評価に影響を与えるとされています。
つまり、従来のように今現在いくら儲かっているのかという財務情報だけの視点では、もはや企業の持続的な成長力や将来の価値を評価できない時代になっているということです。
中小企業庁も、生産性向上や事業承継を目的とした施策を展開する中で、税務だけでなく労務、法務、金融など多岐にわたる専門家による総合的なアドバイスの重要性を強調しています。
こうした国の動きからも、一人の専門家だけに頼る時代は終わりつつあるということがわかります。
一人の専門家だけでは見えない死角があります
税理士は税金と数字のプロフェッショナルです。これは間違いありません。
ただ、たとえばこういった分野については、他の専門家のほうが詳しいケースがほとんどです。
・助成金や補助金の最新情報は、社労士や行政書士が得意です
・採用や評価制度の設計は、社労士や人事コンサルタントの専門領域です
・事業承継の法律面は、弁護士や司法書士に相談する必要があります。
(中小企業庁も、相続税・贈与税の対策だけでなく法務面の検討が不可欠であると指導しています )
・金融機関の評価ポイントは、銀行の担当者が一番よく知っています
一方で、保険や投資商品を扱う専門家は、お金を増やす仕組みには詳しいものの、税務上の取り扱いや、将来お金を受け取るときの税金についてまでは、必ずしも詳しくない場合もあります。
それぞれの専門家が自分の得意分野だけでアドバイスをすると、こういったちぐはぐな結果が起こりがちです。
・保険は節税になると聞いて加入したけれど、お金を受け取るときに思った以上に税金がかかってしまった
・助成金はもらえたけれど、翌年以降の人件費負担が重くなって困った
・節税を優先して利益を圧縮した結果、銀行からの評価が下がって融資が通りにくくなった
こういった失敗、実は珍しくありません。
金融機関が見ているのは事業性評価です
金融庁は近年、金融機関に対して、担保や過去の決算書だけでなく、事業の将来性や経営計画を評価する事業性評価を重視するよう推進しています。
この評価では、将来にわたる安定した利益や返済能力を示すことが重要になります。
さらに、企業が策定した経営計画の実現性も問われるため、計画の段階から税理士や社労士を含む外部の専門家が連携して関与することが、企業の信頼性を高める要因となります。
つまり、バラバラの専門家に相談するのではなく、チームとして一つの方向を向いて動くことが、金融機関からの評価にも直結するということです。
シナジー節税のキーワードは「第3案」を探すこと
『7つの習慣』の第6の習慣では、「自分の案か、相手の案か」という二者択一ではなく、お互いの違いを生かした第3案を探すことが大切だと説かれています。
節税でも、まったく同じことが言えます。
たとえば、税理士の視点からは税金と決算書のバランスを整えたいと考えます。金融機関の視点からは安定した利益と返済能力を重視したいと見ています。保険や投資の専門家は将来の備えや運用を厚くしたいと提案してきます。
このとき、どれか一つを選ぶのではなく、「どう組み合わせると、一番会社にお金が残るだろうか?」という第3案を探すのが、シナジー節税の考え方です。
具体的には、こんなイメージです。
・すべてを保険で節税するのではなく、設備投資、社員教育への投資にも分散させる
(人的資本への投資として、金融機関からの評価も向上します)
・銀行からの借入と、内部留保の積み増しと、将来の退職金準備を、トータルで設計する
こういった組み合わせは、一人の専門家だけではなかなか見えてきません。だからこそ、複数の専門家の知恵を集めることが大切です。
チームで話す時間を意識的につくりましょう
シナジーは、自然に生まれるものではありません。意識的に時間を取らないと、実現しません。
『7つの習慣』でいう第II領域(緊急ではないけれど重要なこと)として、しっかり予定に組み込むことをおすすめします。
私がおすすめしているのは、年に1回は専門家を同じテーブルに集めることです。
その場で、次のようなことを共有してみてください。
・今後3〜5年の会社の方向性
・社長ご自身のライフプラン(いつ頃引退したいか、など)
・資金繰りや投資の希望
・人材戦略や福利厚生の方針
税理士、社労士、銀行の担当者、場合によっては保険の担当者など。全員が同じ前提を共有したうえで話し合うと、こんなことがクリアになってきます。
・会社としてどこまでリスクを取れるのか
・どのタイミングで節税と投資をするのがベストか
・どれくらいの手元資金を用意しておくべきか
こうした全体最適の案は、バラバラに相談していたのでは出てきません。
豊かさマインドを持った専門家を選びましょう
『7つの習慣』の第4の習慣に出てくる「豊かさマインド」という考え方も、ここに関わってきます。
シナジーを生み出すには、自分の取り分を守る専門家ではなく、みんなが得をする案を探せる専門家と組む必要があります。
たとえば、こんな専門家は要注意です。
・他の専門家の悪口ばかり言う
・自分のサービスだけを売り込もうとする
・他の士業と連携する気がまったくない
こういう方と組んでも、残念ながらシナジーは生まれません。
逆に、こんなふうに言ってくれる専門家は、長期的に見ると会社にとって大きなプラスになります。
「この部分は税理士さんにも確認しましょう」
「銀行さんの意見も聞きながら決めていきましょう」
「社長の人生設計も含めて、一緒に考えませんか?」
こういった姿勢を持った専門家を、ぜひ大切にしてください。
まとめ
一人の専門家だけに頼ると、どうしてもその人の得意分野だけで節税が決まってしまいます。
いま、経済産業省や金融庁が推進しているように、企業価値は財務情報だけでなく、人的資本や事業の将来性といった非財務情報も含めて評価される時代です。
税理士、社労士、銀行、保険、ITなど、さまざまな専門家を巻き込んで「第3案」を探すことで、会社にお金が残りやすくなります。
そして、シナジー節税を実現するには、みんなの得を考えられる専門家と組むことが欠かせません。
節税は税理士に任せるものという発想から、会社のチーム全体で設計するものへ。
この考え方の転換が、長くお金が残る会社をつくっていきます。