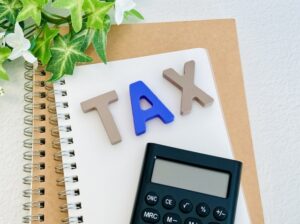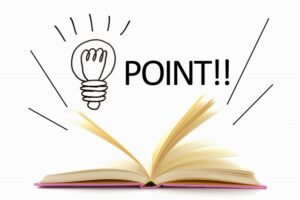売上はあるのにお金が残らない社長へ、『7つの習慣』から学ぶ3つの発想の転換

「今月も頑張って売上を伸ばしたのに、気づけば通帳の残高が増えていない…」
こんな経験はありませんか?
実は、多くの経営者の方が同じような悩みを抱えていらっしゃいます。
中小企業庁の『2024年版 中小企業白書』によると、中小企業の売上高は回復傾向にあるものの、原材料価格やエネルギー価格の高騰に対して十分な価格転嫁ができていない企業では、収益性が圧迫されている実態が報告されています。
つまり、売上は増えても利益が残らないという現象は、今の日本の中小企業に広く見られる課題です。
そしてこの問題、節税のテクニックだけでは解決できません。
大切なのは、お金に対する向き合い方、そのものを書き換えることです。
今回は、スティーブン・R・コヴィー博士の著書『7つの習慣』の考え方をベースに、お金が残る経営へ3つの発想の転換についてご紹介します。
まずは自分の選択を見つめ直す(インサイド・アウト)
最初の発想の転換は、インサイド・アウトの発想です。
お金が残らないとき、私たちはついついこう考えがちです。
- 税金が高すぎるから仕方ない
- 景気が悪いから利益が出ない
- 社員がなかなか育ってくれない
これらはアウトサイド・イン、つまり外側に原因を求める考え方です。
一方で、インサイド・アウトの考え方は、まず自分の内側から見直していく発想です。
- 自社の利益構造に問題はないか?
- お金の使い方は適切だろうか?
- 節税の判断は本当に正しかったのか?
20年以上、多くの経営者の方の節税相談に乗ってきて気づいたことがあります。
それは、本当にお金が残る経営者ほど、外部のせいにする前に、ご自身の選択を振り返っているということです。
たとえば、先ほどの『中小企業白書』では、価格転嫁ができている企業とできていない企業の間で、経常利益率に明確な差が生じていることが示されています。
つまり「売上の構造が薄利多売になっていないか?」という自社に対する問いかけは、統計的にも裏付けられた重要なポイントです。
こうした問いに真っすぐ向き合わない限り、どんなに優れた節税策でもその場しのぎで終わり、お金を残すための根本的な解決とはなりません。
未来を変える選択をする(第II領域への投資)
2つ目の発想の転換は、第II領域にお金と時間を投資することです。
第II領域とは、緊急ではないけれど、重要なことです。
会社経営においては、お金を生む仕組みと節税の仕組みづくりがこれに当たります。
たとえば、こんなことです。
- リピート客を増やす仕組みづくり
- 粗利率を上げるための値決めの情報収集
- 年間を通じた節税・投資の計画立案
- 社員教育やマニュアルの整備
こういった取り組みは、今すぐやらなくても会社は回ります。
そのためつい後回しにしてしまいがちです。
しかし、これらをやらないまま売上だけを追いかけ続けると、次のような状況に陥ってしまいます。
- 忙しいのに利益が出ない
- 決算が近づくと節税で慌てる、または節税に失敗する
- 借入に頼らないと資金が回らない
第II領域への投資効果は、公的な統計でも明確に実証されています。
『2024年版 中小企業白書』の分析によると、有形固定資産(機械など)だけでなく、無形資産(ヒト・ブランド・組織構造・ソフトウェアなど)へ投資を行っている企業ほど、労働生産性が高い傾向にあります。
特に注目すべきは、人への投資を実施している企業は、実施していない企業に比べて売上高増加率が高いというデータです。
つまり、社員教育やマニュアルの整備は、実際に経営数値に貢献するということです。
第II領域にお金を使うことは、節税以上にリターンを生む投資です。
税金を減らす工夫をする前に、まずは利益とキャッシュそのものを増やす仕組みづくりに時間とお金を使う。
これが、一番効率の良いお金を増やす方法です。
税金と共存しながら成長する(豊かさマインド)
3つ目の発想の転換は、豊かさマインドです。
「税金を払うのは損だ」「できるだけゼロにしたい」――こう考えるのは自然なことです。
しかし、この考え方そのものが、会社の成長を止めてしまうことがあります。
視点を変えてみましょう。
税金を払っているということは、それだけ利益が出ているという証拠です。
銀行の担当者から見れば、しっかり利益を出して納税している会社は、非常に信頼度の高い会社です。
豊かさマインドとは、次のような発想です。
「税金を払えるほど稼げる会社になろう」
「税金も、社員への還元も、投資も、全部できる会社を目指そう」
その上で、こんなスタンスで節税と付き合います。
- 無駄な税金は減らす
- 将来への投資になる節税だけを選ぶ
- 制度や優遇措置は遠慮なく使う
今、国が推し進めている税制措置は、まさにこの豊かさマインドを後押しするものになっています。
たとえば、賃上げ促進税制では、従業員の給与を上げた場合、その増加額の一部を法人税から控除できます。
令和6年度改正では、赤字の中小企業でも翌期以降に繰り越して控除が可能になるなど、制度が大幅に強化されました。
これは社員への還元を節税につなげる仕組みです。
また、中小企業経営強化税制では、認定を受けた経営力向上計画に基づき設備投資を行った場合、即時償却または税額控除が認められています。
こうした制度を活用することで、投資も税金対策も、どちらも実現するという豊かさマインドの経営が可能になります。
節税の効果を上げる3つの質問
最後に、真に効果的な節税をするためのシンプルな質問を3つご紹介します。
何か節税の話が出たとき、この3つの質問を自分に投げかけてみてください。
この支出は、未来の利益を生むか?
それは単なる消費でしょうか、それとも利益を生む投資でしょうか?
この節税は、手元資金を減らさないか?
減税額と実際のキャッシュアウトを比べていますか?
この判断は、経営の自由度を狭めないか?
長期的な資金拘束によって、将来の経営の選択肢を狭めたりしませんか?
この3つの質問に「はい」と言えるかどうか。
ここに、「節税でお金を残す会社」と「節税しているのにお金が残らない会社」の分かれ目があります。
もし、今のお金の流れに不安を感じていらっしゃるのなら、ぜひ一度、これらの発想の転換を試してみてください。