「節税すればするほどお金が減る」中小企業がハマる落とし穴と抜け出す方法
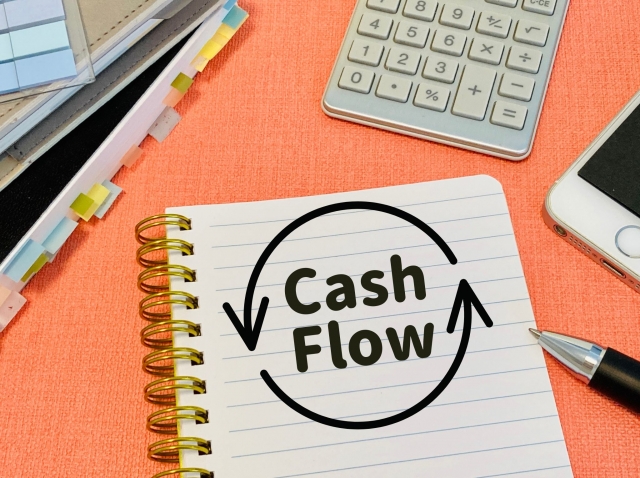
中小企業の経営者の多くが、毎年決算期が近づくと「税金がもったいないから、何か経費を使わないと」と焦ります。
売上は伸びているのに、なぜか会社にお金が残らない。
この繰り返しに心当たりがある方は、ぜひ最後まで読んでください。
その原因は、「税金を減らす=得をしている」という思い込みと、「利益」と「現金」の違いを正しく理解していないことにあります。
この記事では、経費の使い方を根本から見直し、「節税のためにお金を使ったのに、お金が減っていく」という矛盾した状態から抜け出すための考え方をお伝えします。
税金が減っても、手元のお金は減る「節税の罠」
まず、よくある会話を紹介します。
経営者A「今期、利益出ちゃいそうだから、パソコンでも買っておこうかな」
経営者B「うちは法人保険入ったよ。税金減るし、退職のとき返って来るって言うし」
このような判断の裏には「税金を払うくらいなら経費を使った方が得だろう」という感覚があります。
しかし、これは大きな誤解です。
この考え方に基づいた支出は、ほとんどの場合、お金を使って得した気になっているだけで終わります。実際には、会社のキャッシュ(現金)を大きく減らしてしまっているのです。
数字で見る「節税の罠」
たとえば、利益100万円に対して税率が30%だった場合、税金は30万円です。
では、80万円の経費を無理やり使って利益を20万円に抑えたら?
税金は6万円になります。
一見、24万円の節税に成功したように見えますが、実際に手元に残るお金はこうなります。
- 節税前:100万円 − 30万円 = 70万円の現金
- 節税後:100万円 − 80万円 − 6万円 = 14万円の現金
24万円得するために、80万円使ってしまった。
つまり、手元から56万円が消えたのです。
これが、「節税すればするほどお金が減る」構造の正体です。
このように、税金が減ったことに満足してしまい、結果的に会社の財務状況を悪化させていることに、多くの経営者が気づいていません。
利益と現金のズレを知ることが経営の第一歩
ここで押さえておくべきは、「帳簿上の利益」と「実際のキャッシュ(現金)」は一致しない、ということです。
会計は「利益」という決算書上の数字を出すためにルールに基づいて処理されますが、現金の動きとは必ずしも連動しません。
現金が減るのに経費にならない例
- 借入金の元本返済:帳簿上は経費にならないが、現金は確実に出ていく。
- 在庫購入:資産として計上され、売れる時まで経費化されない。
- 設備投資:資産として計上され、数年かけて減価償却によって経費化される。
これらの要因を無視して、「帳簿上の利益がある=お金がある」と考えてしまうと、大きな判断ミスにつながります。
特に中小企業では、経営者自らがキャッシュ管理も担っていることが多く、現金の流れへの理解が経営の安定に直結します。
「消費としての節税」ではなく「投資としての節税」を考える
節税を考える際に大切なのは、支出の性質を見極めることです。
節税支出が、将来の会社の利益や成長にどう繋がるかを判断基準にするべきです。
ここで言う理想的な節税とは、将来の利益を生む、または経営者・従業員の幸福度を高める経費であること。そして、その支出が税務上の優遇を受けられるものであれば、なお良しです。
「効果的な経費」の具体例
- 未来の利益を生む支出:
- 営業ツールの導入(営業効率の改善)
- ウェブサイトの改善やSEO対策(見込み客の流入増加)
- 従業員の幸福度を上げる支出:
- 福利厚生の充実(社員の定着)
- 教育研修(スキルアップと業務効率化)
- 業務の効率化・自動化:
- クラウド会計システム導入
- AIツール活用
- タスク管理ツールの導入
- 集客資産の構築:
- YouTubeチャンネル開設
- メルマガシステムの整備
- ノウハウ書籍の出版
節税というより経営の武器となる支出を選ぶ。この視点が、未来のキャッシュを守るカギとなります。
その支出、本当に「投資」ですか?3つのチェックリスト
経費を使う前に、次の3つの質問をしてください。
- この支出は、未来の利益を生むか?
- 売上の増加や、コスト削減、業務効率の向上につながるか?
- 売上の増加や、コスト削減、業務効率の向上につながるか?
- この支出は、未来のキャッシュを増やすか?
- 節税によって得られる現金の増加額よりも、支出額が大きくなっていないか?
- 節税によって得られる現金の増加額よりも、支出額が大きくなっていないか?
- この支出は、会社の自由度を高めるか?
- 長期間の資金拘束がなく、経営判断の幅を狭めないか?
たとえば、過度な法人保険。将来的に返戻金があるかもしれませんが、長期間資金が拘束され、途中で使えないとなれば、会社の自由度を下げてしまいます。
- 長期間の資金拘束がなく、経営判断の幅を狭めないか?
キャッシュが残る会社に変えるには?
重要なのは、節税テクニックではなく、まず「利益構造」と「支出設計」を見直すことです。
利益構造を変える
- 労働集約的な単発サービスから、継続課金型へ(例:顧問契約)
- 対面サービスから、コンテンツ販売やオンライン講座へ
- 1対1対応から、1対多のモデルへ
このように利益効率を高め、継続的かつ自動的にお金が入る仕組みを作ることが重要です。
支出設計を変える
- 惰性で使う経費をなくし、未来に効く支出へシフト
- 節税のために慌てて使うのではなく、戦略に基づいて計画的に使う
- 月次決算などで利益を常に把握し、タイムリーに判断する
お金を残すための節税を実現するには、このように会社全体の支出設計を見直す必要があります。
まとめ:節税は「未来に効く支出」の設計から始まる
「税金がもったいないから、とりあえず何か買おう」は、会社のお金を確実に減らしていきます。
本当に目指すべきなのは、税金をきちんと払いながら、なお現金が潤沢に残る強い会社です。
そのためには、節税を目的にするのではなく、未来への投資としての支出設計をすることが大切です。さらに、その支出が戦略的に設計され、自社のビジネスモデルと一貫性があることが重要です。
この考え方を実践すれば、節税という行為が単なる「その場しのぎの支出」ではなく、「会社の成長のための布石」へと変わります。











