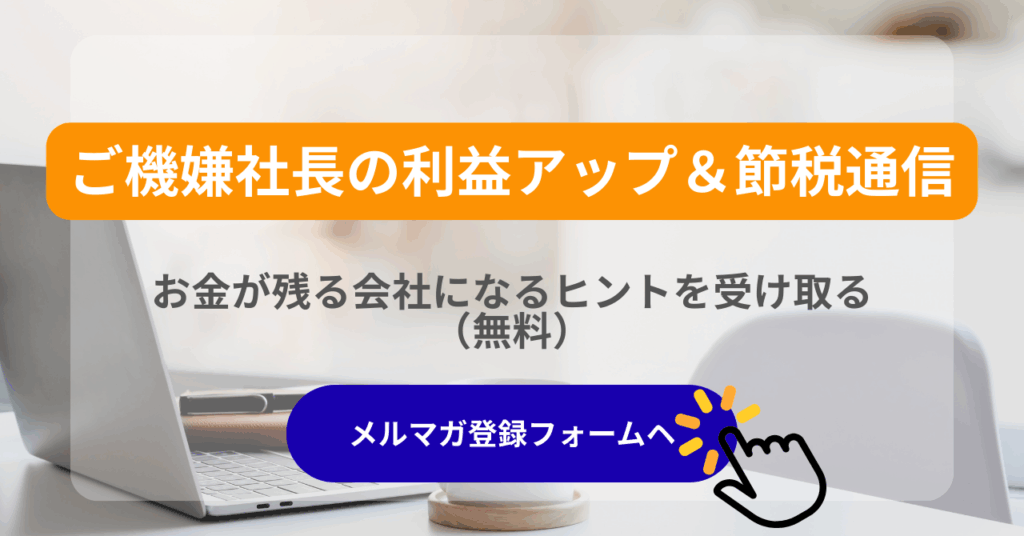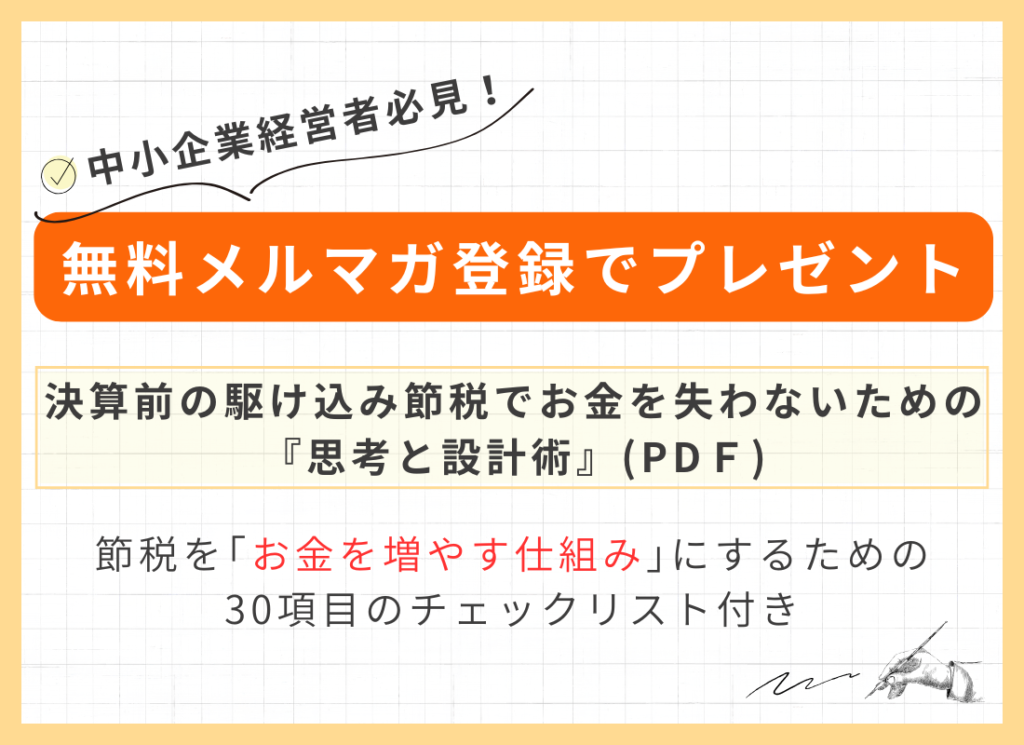社宅を導入するとなぜ節税になる? 中小企業経営者のための基礎知識

はじめに:なぜ今、社宅制度が注目されているのか
従業員の採用や定着に頭を悩ませている経営者の方は多いのではないでしょうか。
給与を上げたいけれど、そう簡単にはいかない。
そんなとき、ぜひ検討していただきたいのが社宅制度です。
社宅制度は、会社が住居を用意し、従業員に貸し出すという福利厚生の一つです。
従業員にとっては家賃負担が軽くなり、会社にとってはうまく設計すれば節税効果も期待できます。
まさに双方にメリットのある制度といえます。
しかし、この制度には税金に関するルールがあり、正しく理解していないと思わぬ税負担が生じることもあります。
今回は、社宅制度と税金の関係について、専門用語をできるだけ使わずにわかりやすく解説します。
社宅に税金が関係する理由
まず、なぜ社宅に税金が関係してくるのかを押さえておきましょう。
税法には経済的利益という考え方があります。
これは、お金そのものではなくても、金銭的な価値のあるメリットを受け取った場合、それを給与と同じように扱うという考え方です。
たとえば、本来であれば従業員が毎月10万円の家賃を自分で支払うところ、会社が社宅を無償で貸してくれれば、その10万円分を節約できます。
この節約できた金額が経済的利益にあたり、給与として課税される可能性が出てくるのです。
つまり、社宅をただ無償で貸すだけでは、従業員の税負担が増えてしまうことがあります。
では、どうすれば課税を避けられるのでしょうか。
その鍵となるのが、次に説明する最低限支払うべき家賃の考え方です。
課税されないための最低ライン:賃貸料相当額とは
社宅を役員・従業員に貸す際、給与として課税されないためには、役員・従業員から一定額以上の家賃を徴収する必要があります。
この最低限支払ってもらうべき家賃のことを、賃貸料相当額と呼んでいます。
この金額は、国が定めた計算式に基づいて算出されます。
計算には主に3つの要素が使われます。
- 建物の価値
これは固定資産税の評価額を使います。 - 土地の価値
建物が建っている土地にも価値があるため、その分も考慮されます。こちらも固定資産税の評価額を使います。 - 建物の広さ
床面積が広いほど価値が高くなるため、計算に反映されます。
これら3要素を使って計算した賃貸料相当額は、オーナーへの家賃支払額と比べ、かなり低く算出されることがほとんどです。
この個人が負担する賃料相当額と会社がオーナーへ支払う家賃との差額が、個人にとっての実質的な非課税収入となります。
なお、役員が社宅を利用する場合は、計算方法が少し複雑になります。
社宅の床面積によって計算式が変わり、ざっくり木造の建物の場合は床面積が132平方メートル以下、鉄筋コンクリート造の建物の場合は99平方メートル以下かどうかが重要です。
上記の面積を超えると家賃の個人負担割合が大きくなる可能性(オーナーへの支払家賃の50%)があるので、役員の社宅を契約する際には床面積に注意しましょう。
なお、マンション・アパートの場合は共用部分(廊下やロビーなど)の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定するという点も要注意です。
自室の床面積は99平方メートル以下でも、広々としたロビーなどがあるマンションでは共用部分を加えて99平方メートルを超えるケースは多くあります。
また、床面積が240平方メートルを超えたり、プール付きの物件など、一般的に豪華な社宅と見なされるものについては、これらの計算方法は適用されず、オーナーに支払う家賃を全額個人で負担しなければいけなくなる可能性があります。
必ず賃貸借契約は物件オーナーと会社が直接結びましょう。そうでなければ、社宅としては認められません。
役員・従業員が支払う家賃で変わる3つのパターン
役員・従業員が実際に支払う家賃と賃貸料相当額の関係によって、税金の扱いは3つのパターンに分かれます。
それぞれ見ていきましょう。
パターン1:個人負担ゼロ
役員・従業員から家賃を徴収しない、いわゆる無償貸与の場合です。
この場合、賃貸料相当額の全額が給与として扱われ、所得税や住民税の課税対象となります。
役員・従業員にとっては、給与の手取りが減ってしまう可能性があります。
パターン2:賃貸料相当額より低い家賃を個人負担する
役員・従業員から家賃を徴収しているものの、その金額が賃貸料相当額に満たない場合です。
賃貸料相当額と実際に支払った家賃との差額が給与として扱われ、課税対象となります。
パターン3:賃貸料相当額以上の家賃を個人負担する
役員・従業員から賃貸料相当額以上の家賃を徴収している場合です。
この場合、給与として課税されることはありません。
会社からの家賃補助分が非課税となるため、役員・従業員にとって最もメリットの大きいパターンです。
多くの会社では、このパターン3に該当するように家賃を設定しています。
制度を導入する際は、必ず賃貸料相当額を正しく計算し、適切な家賃設定を行うことが重要です。
住宅手当との違いを理解する
福利厚生として住居費を補助する方法には、社宅制度のほかに住宅手当を支給するという選択肢もあります。
この2つには税金面で大きな違いがあります。
社宅制度の場合、従業員が賃貸料相当額以上の家賃を支払っていれば、会社が負担している家賃補助分は給与として課税されません。
一方、住宅手当の場合は、支給された金額の全額が給与として扱われます。当然、所得税や住民税の課税対象です。
たとえば、会社が月5万円の住居費補助を考えているとします。
住宅手当として5万円を支給すれば、その全額に税金がかかります。
しかし、社宅制度を活用して適切に家賃を設定すれば、同じ5万円相当の補助を非課税で提供できる可能性があります。
なお、社宅家賃の会社負担分については社会保険料もかかりません。
これは会社・個人双方にとって税金面以外での大きなメリットです。
このように、同じ金額を使うのであれば、社宅制度の方が税制面で有利になるケースが多いです。
ただし、従業員の入退社が多い会社の場合は、社宅契約の名義変更などの事務手続きが煩雑になりますので、この点には注意して導入しましょう。
家具付き社宅の注意点
社宅とあわせて、テレビやベッドなどの家具も会社が用意して貸し出す場合があります。
この場合、家具から得られる利益は社宅の家賃とは別の経済的利益として扱われます。
会社が所有する家具であれば、その減価償却費相当額をもとに価値が計算されます。
外部からリースしている家具であれば、リース料相当額が基準となります。
いずれの場合も、給与として課税される可能性がありますので、家具付き社宅を検討する際は注意が必要です。
まとめ:社宅制度を正しく活用するために
ここまで社宅制度と税金の関係について解説してきました。
最後に重要なポイントを振り返っておきます。
まず、会社が役員・従業員の家賃を負担することは、税法上は経済的利益と見なされます。
そのため、ただ無償で社宅を貸すだけでは節税にならず、むしろ役員・従業員の税負担が増えます。
次に、賃貸料相当額以上の家賃を従業員から徴収すれば、給与として課税されることはありません。
このルールを守ることで、会社も役員・従業員もメリットを享受できます。
そして、現金で支給する住宅手当よりも、社宅制度の方が税制面で有利になるケースが多いです。
福利厚生の充実を検討している場合は、社宅制度の導入を選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。
社宅制度は、役員・従業員の生活を支えながら、会社としても効果的な人材確保策となりえます。
ただし、税金のルールを正しく理解し、適切に運用することが大前提です。
制度の導入や運用に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。
【免責事項】
本記事は2025年12月時点の税制に基づいて作成されています。
税制は随時改正されるため、実際の適用にあたっては最新の情報を確認し、必ず税理士等の専門家にご相談ください。