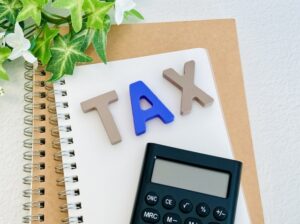第7の習慣と税金リテラシー―学びに投資する社長ほど、なぜお金が残るのか
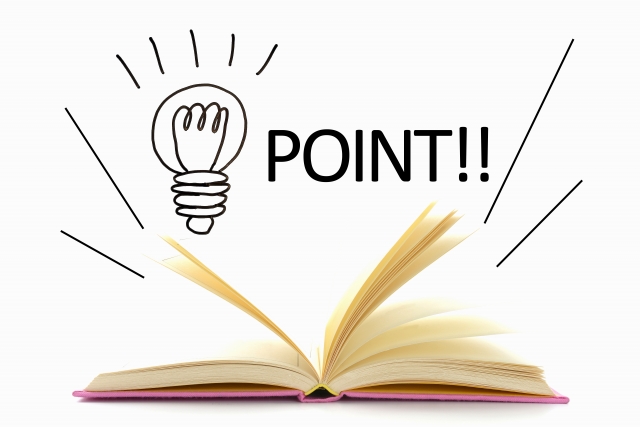
『7つの習慣』の最後の習慣、「刃を研ぐ」をご存知でしょうか。
肉体、精神、知性、社会・情緒という4つの側面をバランスよく磨き続けることの大切さを説いています。
私は税理士として、多くの中小企業の社長とお付き合いをさせていただく中で、この4つの中でも「知性」の部分、つまり税金やお金の知識を自分で学び続けることが、経営の成果に大きな差を生むと実感しています。
今回は、なぜ税金リテラシーを高めることが社長にとって重要なのか、そしてどうすれば無理なく学び続けられるのかについて、ご紹介します。。
「税金はよくわからないから税理士に丸投げ」は、ちょっと危険かもしれません
もちろん、税金の計算や申告書の作成は私たち税理士の仕事です。すべてをご自身でやる必要は全くありません。
ただ、たとえば次のようなことを全く知らないまま、「すべてお任せします」という状態になっているとしたら、少し立ち止まって考えてみてください。
- 税金の基本的な仕組み
- 決算書のざっくりとした読み方
- 節税が資金繰りにどう影響するか
なぜなら、どれだけ優秀で信頼できる税理士であっても、社長ご自身が何を大事にしているのか、3年後、5年後にどんな会社にしたいのか、どこまでリスクを取れるのかといったことは、社長ご本人ほど深くは理解できないからです。
知識がほとんどないまま丸投げしてしまうと、こんなことが起こりがちです。
- 短期の節税には成功したけれど、将来の資金繰りが苦しくなってしまった
- 税金は減ったけれど、銀行からの評価が下がって融資が受けにくくなった
- 社長の老後に必要なお金が、実は全く足りていなかった
「こんなはずじゃなかった…」という結果にならないためにも、最低限の税金リテラシーは身につけておきたいところです。
「1日15分」で刃を研ぐ―税金リテラシーの鍛え方
第7の習慣は、毎日の小さな積み重ねです。
税金やお金の知識も同じで、一気に専門家レベルを目指す必要はありません。
私がお勧めしているのは、次の3つの習慣です。
毎日15分だけ、お金・経営・税金に関する本や記事を読む
朝のコーヒータイムや、寝る前のちょっとした時間でかまいません。専門書である必要もなく、経営者向けのやさしい解説記事やビジネス書で十分です。
毎月1回、税理士と「雑談ベース」で数字の話をする時間をつくる
堅苦しい打ち合わせではなく、「最近、気になってることがあるんですけど」といった感じで、気軽に質問できる時間を持つことが大切です。
四半期に1回、自社の決算書(試算表)をご自身の言葉で説明してみる
誰かに説明するつもりで、数字を眺めてみる。
最初はうまく言えなくても大丈夫です。なんとなく、こういう仕組みなんだなとイメージが持てるだけでも、節税の判断が大きく変わってきます。
完璧に理解しようとしなくても大丈夫です。継続することで、少しずつ自分の中に知識の土台ができあがっていきます。
学び続けることで「節税の見極め力」が格段に高まります
学び続けている社長と、学んでいない社長の違いが一番はっきり出るのが、節税の話を聞いたときの反応です。
学んでいない社長は、こんな反応をしがちです。
「税金が減るなら、とりあえずやってみようかな」
一方、学び続けている社長は、こんな質問をされます。
「それをやると資金繰りはどう変わりますか?」
「出口のときの税金はどうなりますか?」
「銀行の目線から見たとき、どう評価されるでしょうか?」
後者の社長は、今、目の前の節税額だけでなく、実際に出ていくお金、将来の納税額、会社の信用など、さまざまな角度から総合的に判断できるようになっています。
これは、特別な才能や経営センスの問題ではありません。
日々の刃を研ぐ時間の積み重ねが、自然とこうした質問へと繋がっています。
心と体を整えることも、節税につながっています
第7の習慣は、知性だけではありません。
- 肉体(健康)
- 精神(価値観やミッション)
- 社会・情緒(人間関係)
一見、節税とは関係なさそうに思えますが、ここにも深いつながりがあります。
体調が悪いと、判断が短期的になりがちです。
心がすり減っていると、今さえ良ければいいという節税に走りやすくなります。
人間関係が狭いと、相談できる相手が税理士しかおらず、視野も狭くなってしまいます。
逆に、こんな状態を保てていたらどうでしょうか。
- 健康でエネルギーがある
- 自分なりの経営の軸がある
- 信頼できる仲間や専門家がいる
こういう状態だと、節税の判断も自然と長期目線になっていきます。
今期だけ良ければOKではなく、「5年後、10年後に会社と自分の人生がどうありたいか」という終わりから逆算して、お金の使い方を選べるようになります。
学ぶこと自体が会社の大きな財産です
多くの社長は、設備や広告、人材にはしっかりお金を使いますが、ご自身の学びへの投資は控えめです。
しかし、社長ご自身が、決算書が読めるようになること、税金の基本がわかるようになること、資金繰りの見通しが自分で立てられるようになること。
これらはすべて、会社にとって大きな財産になると私は考えています。
なぜなら、一度身につけてしまえば、その知識は毎年の経営判断に何度も何度も使えるからです。
そして、その経営判断が新たなお金を生むからです。
まとめ
- 税金をすべて丸投げするのはリスクがあり、最低限の「税金リテラシー」は社長自身の武器になる
- 毎日15分、毎月1回、四半期に1回の刃を研ぐ習慣で、節税の見極め力が格段に上がる
- 心と体、知性、人間関係のバランスを整えることも、長期目線の節税判断には欠かせない
節税のテクニックを追いかける前に、まずはご自身である程度節税策の良し悪しを感じ取れる知識を持つこと。
それが、より多くのお金が会社に残る道だと、私は考えています。
ぜひ、今日から少しずつ、学びの時間を作ってみてください。
我々税理士も懸命に学び続けます。