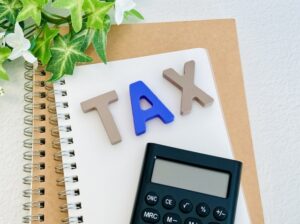「黄金の卵」と「節税」の勘違い―PとPCのバランスから考えるお金が残る会社の作り方

売上は上がっているのに、お金が残らない理由
中小企業の社長さんとお話ししていると、こんなお悩みをよくお聞きします。
「売上は伸びているんですけど、なぜか手元にお金が残らないんですよね…」
実は、この悩みの背景には2つの思い込みが潜んでいることが多いです。
1つ目は「売上さえ伸びれば、会社はどんどん良くなる」という思い込み。
2つ目は「節税さえしっかりやれば、お金が残る」という思い込みです。
2025年版「中小企業白書」でも、中小企業の経常利益は長期的に上昇傾向にあるものの、大企業との差は拡大しており、約30年ぶりの賃上げの中で労働分配率は8割近くに達していると報告されています。
つまり、多くの中小企業が「売上は上がっても余力が生まれない」という状況に直面しています。
『7つの習慣』に学ぶ、PとPCのバランス
スティーブン・R・コヴィー博士の『7つの習慣』という本をご存知でしょうか。この本の中に「黄金の卵とガチョウ」という有名なたとえ話が出てきます。
黄金の卵=目の前の成果(P)
ガチョウ=その成果を生み出し続ける力(PC)
という関係です。
目先の黄金の卵ばかりを追いかけてガチョウを酷使してしまうと、やがてガチョウは疲れ果てて卵を産めなくなってしまいます。
そのため、P(成果)とPC(成果を生み出す能力)のバランスをとることが大切です。
ところが経営の現場では、「売上という黄金の卵」や「節税という黄金の卵」ばかりに目が向いてしまい、
本当に大切なガチョウである
「利益が安定して出る仕組み」「数字を正しく見る力」「賢い節税の判断ができる力」
といった会社の体力を強化するための投資が、どうしても後回しになりがちです。
中小企業白書でも、従来のコストカット戦略は限界を迎えており、「積極的な設備投資・デジタル化(DX)」や「適切な価格設定」によって労働生産性を高めることが不可欠だと分析されています。
これはまさに、PCの強化が中小企業の経営では求められているということです。
節税のつもりがガチョウを弱らせている
決算が近づくと、こんなご相談をよくいただきます。
「税金を払うくらいなら、何か経費を使ったほうがお得ですよね?」
そのお気持ちは、とてもよくわかります。私もできることなら税金は払いたくないです。
しかし、ここで一度冷静に数字を見てみましょう。
たとえば利益が100万円出ていて、税率が30%だったとします。
何もしなければ、税金は30万円です。
手元には70万円が残ります。
ここで「節税しなきゃ!」と考えて、80万円の支出をしたらどうなるでしょうか?
利益は20万円に減り、税金も6万円に減ります。
確かに「24万円も節税できた!」と感じるかもしれません。
しかし実際に手元に残るお金は…
100万円 − 80万円(支出)− 6万円(税金)= 14万円
何もしなければ70万円残せたはずが、14万円しか残っていない。
つまり、節税のつもりで56万円も失ってしまったことになります。
これはまさに、黄金の卵(節税効果)を欲しがるあまり、ガチョウ(会社の資金力)を弱らせてしまっている状態です。
「良い節税」と「悪い節税」を見分けるコツ
では、どうすればいいのでしょうか。
ここで『7つの習慣』のP/PCバランスの考え方を、節税にそのまま当てはめてみます。
P(成果)=今年の税金がどれだけ減るか
PC(能力)=会社がお金を生み出し続ける力が高まるか
この2つの視点で見ると、節税は大きく2つのパターンに分かれます。
【パターン①】Pはプラスだけど、PCはマイナスになる節税
税金は確かに減るけれど、お金も減るし、将来の利益にもつながらない支出です。
たとえば「とりあえず入った保険」「結局使わない備品」「形だけの接待費」などです。
学術研究でも、積極的すぎる節税は企業の財務的な透明性を低下させ、経営者が短期的な利益を優先する結果、長期的な成長投資にマイナスの影響を与える可能性が指摘されています。
【パターン②】PもPCもプラスになる節税(こちらが理想)
税金が減るだけでなく、将来の利益を生み出す力も同時に高まる支出です。
国もこのような投資を強力に後押ししています。
・中小企業経営強化税制
生産性向上設備やIT投資に「即時償却」または「最大10%の税額控除」
・賃上げ促進税制
給与増加額の一部を税額控除(教育訓練費を増やすと控除額の上乗せあり)
・中小企業投資促進税制
機械装置やソフトウェアの取得に「30%特別償却」または「7%税額控除」
これらは「業務の仕組み化」「社員教育」「デジタル化」といったPC強化への投資を行いながら、同時に税負担も軽減できる、まさに理想の節税です。
研究でも、適切な節税は内部資金を留保し、それが企業の効率的な投資の原資となることが示されています。
ゴールから逆算して考える節税
『7つの習慣』では「すべてのものは2度つくられる」と言われています。
1度目は頭の中(設計)、2度目は現実の世界(実行)ということです。
節税も同じです。
「今年の決算、こうなっていたい」というゴールを先に描いておくことが、とても大切です。
たとえば、
・税金を払った後も、最低◯ヶ月分の経費が銀行口座に残っている
・銀行に見せても自信を持てる決算書になっている
これらゴールを先に決めてから、どこにお金を使うべきか、どの節税策を活用するかを選んでいきましょう。
先にゴールを決めること。
これが第2の習慣「終わりを思い描くことから始める」の節税における実践です。
第II領域の時間が、会社の未来を変える
忙しい社長さんほど、日々の業務に追われてしまいます。
急ぎの見積り対応、お客様からのクレーム処理、社員からの急な相談…。
こういった緊急で重要なことで毎日がいっぱいになってしまい、気づけば「あれ、もう決算まで2ヶ月しかない。節税どうしよう?」と慌てることになりがちです。
ここで意識していただきたいのが、第II領域の考え方です。
第II領域とは、
緊急ではないけれど、重要なことです。
節税で言えば、次のようなことが第II領域に当たります。
・月次で利益とキャッシュの流れをチェックする
・1年を通じた投資計画・節税計画を立てる
・税理士と来期の利益の出し方や優遇税制の活用を相談する
・中小企業経営強化税制などの申請準備を進める
こういった時間を確保することこそが、PC(お金を生み出す力)を育てる節税となります。
決算の直前に1回だけ慌てて節税を考えるのではなく、
毎月30分でも構いませんので「今月の利益とお金の残り方はどうか?」「この支出は、本当に未来の利益につながるか?」と確認する習慣をつけてみてください。
税金のせいにしない経営
最後に、一番の土台となる考え方をお伝えします。それは主体性を持った経営です。
「税金が高いから、お金が残らない」 「景気が悪いから仕方ない」
このように考えていると、自分でコントロールできる範囲は広がっていきません。
主体的な経営者は、こう考えます。
・税金を払ってもお金が残る利益の仕組みをつくろう。
・節税をしたいから、前もって税理士に相談しておこう。
・国が用意している優遇税制で自社に適用できるものはないか。
税金そのものは私たちには変えることができません。
しかし、利益の作り方と節税のやり方は、いくらでも主体的に変えることができます。
まとめ
売上や節税という黄金の卵だけを追いかけていると、ガチョウ(お金を生み出す力)はどんどん弱っていきます。
大切なのは、今年いくら節税できるかだけでなく、この支出で、会社の未来を生み出す力は強くなるかという視点で判断することです。
そして、中小企業経営強化税制や賃上げ促進税制など、国が用意しているPもPCもプラスになる節税の仕組みを、賢く活用していきましょう。
節税は、ガチョウを成長させ、繰り返し黄金の卵を産ませるための手段のひとつです。