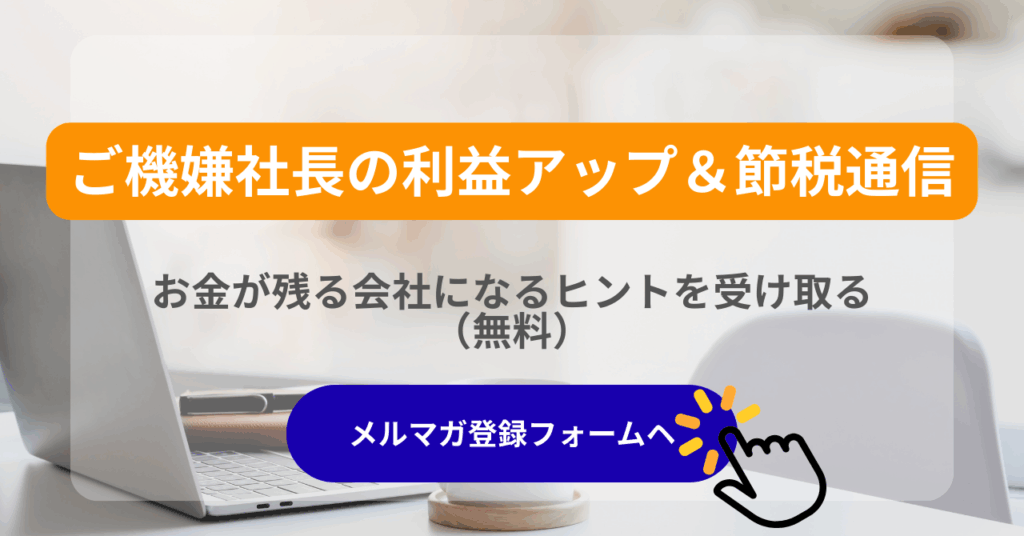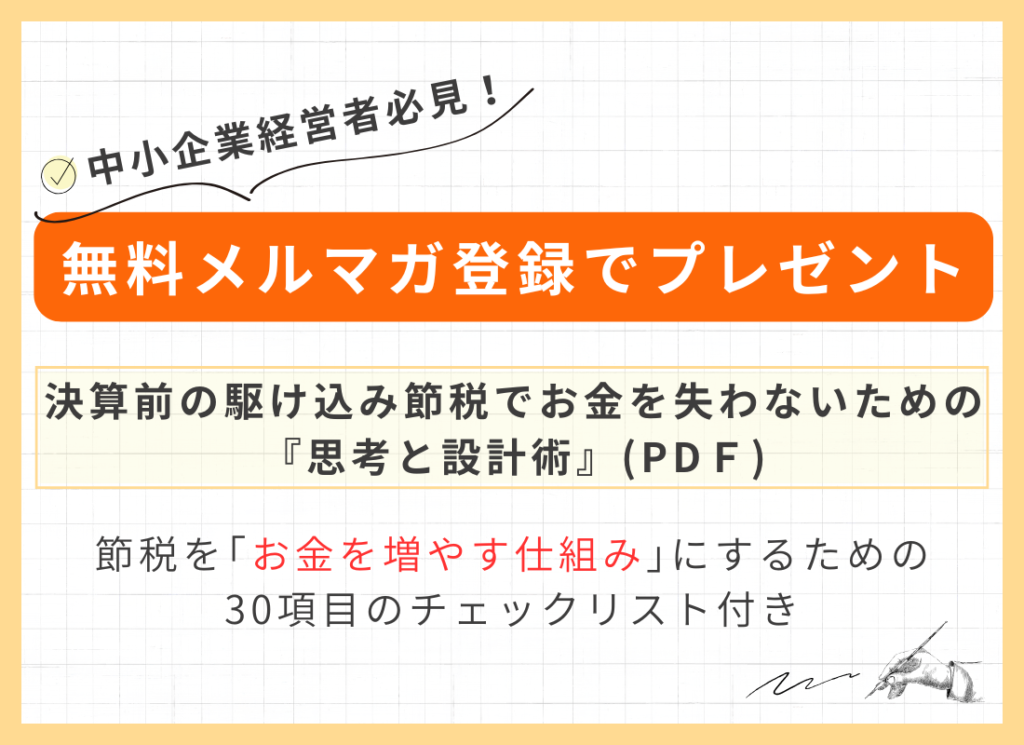追徴10%の人と35%の人は何が違う? うっかりミスと重加算税の境界線を税理士がやさしく解説

税務調査が来ると聞いたとき、多くの経営者の方が不安でいっぱいになるでしょう。
追徴税額はいくらだろう、調査官にどんなことを聞かれるのだろう・・・
25年以上にわたって中小企業の税務を見てきた経験から一つ申し上げたいことがあります。
税務調査において最も気をつけるべきは、重加算税の認定を受けてしまうことです。
通常の申告ミスであれば、過少申告加算税として原則10%のペナルティで済みます。いわば、うっかりミスに対する罰金のようなものでしょう。
ところが、隠蔽(いんぺい)や仮装(かそう)があったと認定されると、ペナルティはいきなり35%から40%に跳ね上がります。
さらに、過去5年以内に重加算税を課されたことがあれば、そこに10%が上乗せされる場合もあります。
本来払うべき税金の半分近い金額を余計に支払うことになると聞けば、その深刻さがわかるはずです。
では、10%で済む人と35%になる人は、いったい何が違うのでしょうか。
今日はこの境界線について、できるだけわかりやすくお話ししていきます。
そもそも重加算税はどんなときに課されるのか
重加算税のルールは、国税通則法第68条という法律に定められています。
少し堅い言葉ですが、大事なところなので確認しておきましょう。
簡単にまとめると、税金の計算のもとになる事実を隠蔽したり仮装したりして、それに基づいた申告書を提出した場合に課されるペナルティです。
ここで出てくる隠蔽と仮装という二つの言葉こそが、まさに境界線を分けるカギでしょう。
隠蔽とは、あるものをないことにする行為のことです
隠蔽を一言でいうと、本当はあるものを、ないことにする行為を指します。
たとえば、こんなケースが該当するでしょう。
売上帳や請求書の控えを捨ててしまう、あるいはどこかに隠してしまう。
帳簿をわざと作らず、売上の一部を記録から外す。
倉庫に在庫があるのに、棚卸しのときにカウントしない。
表の帳簿と裏の帳簿、いわゆる二重帳簿を作る。
ここで一つ、大事なポイントに注目してください。
忙しくて記帳が追いつかなかったというのは、たしかにミスかもしれません。
しかし、見つかるとまずいから書類を処分した、引き出しの奥に隠した、となると話は全く変わってきます。
そこには意図的な行動があるからです。
仮装とは、ないものをあることにする行為のことです
仮装はその逆で、実際にはないものを、あるかのように見せかける行為を指します。
よくあるケースとしては、次のようなものが挙げられるでしょう。
取引先と打ち合わせのうえ、架空の仕入れや架空の経費を作り出す。
請求書や領収書の金額や日付を書き換える。
実在しない人の名前を使って取引を行う。
帳簿に載せない裏金を作って、それを特定の目的に使う。
あなたの会社では、こうした処理に心当たりはないでしょうか。
たとえば、今期の利益が出すぎたからといって、来期分の請求書の日付を今期に書き換えるという行為は、事実を歪めている点で典型的な仮装にあたります。
うっかりミスとの決定的な違いは工作があるかどうかです
ここまで読んで、隠蔽や仮装の意味はわかった、でも普通の計算ミスとはどう区別するの? と思われた方もいるかもしれません。
結論から言うと、その違いは工作と呼べる行動があるかどうかにかかっています。
裁判例でも、隠蔽や仮装と評価できる行為があり、それに合わせた申告がされたかどうかが判断のポイントだと示されてきました。
単に税金が少なかったという結果だけでは、重加算税にはなりません。
申告書を作る前の段階で、隠すための細工や偽装のためのアクションがあったかどうかが問われるわけです。
わかりやすく整理してみましょう。
過少申告加算税(10%)で済むケースは、たとえば売上の集計で電卓の打ち間違いをしてしまった場合です。
あるいは、経費にならないものを勘違いして経費に入れていた場合や、税法の解釈を誤っていた場合も同様でしょう。
これらには、隠したり偽ったりするための工作がありません。
一方、重加算税(35%以上)になるケースでは、明らかに工作が伴っています。
売上の一部を個人の通帳に入金させて会社には報告しなかった。
交際費の明細書に書かれた人数を水増しして書き換えた。
実在しない従業員の名前で人件費を計上して現金を抜き出した。
これらはすべて、事実をねじ曲げるための意図的な行動です。
脱税のつもりがなくても重加算税になることがあります
ここが、今日の記事の中で最も大切なパートになります。
税務調査の場面で、多くの経営者の方がこうおっしゃるでしょう。
たしかに書類の管理はずさんだったかもしれないけれど、脱税しようなんて気持ちは一切なかった、と。
そのお気持ちは痛いほどわかります。
しかし、残念ながらこの反論だけでは重加算税を回避できないケースもあります。
最高裁の判例(昭和62年5月8日判決)で、非常に重要な判断が示されました。
その内容をかみ砕いて説明しましょう。
税金をこれだけ減らしてやろう、という具体的な計算までしていなくても構いません。
売上帳を隠す、書類を書き換える、という行為そのものをわざとやった時点で、重加算税は成立するとされています。
つまり、この売上を除外したら税金がいくら減るかなんて計算していなかったと主張しても、売上を除外するという行為を意図的に行った事実があれば、それだけで十分だということです。
逆に言えば、純粋な計算ミスや転記ミスの場合は、事実を隠蔽したり仮装したりする意図がないため、重加算税の対象にはなりません。
ポイントは行為の意図であり、税額の計算意図ではないという点を覚えておいてください。
グレーゾーンの事例も知っておきましょう
もう少し微妙なケースについても触れておきます。
実際の税務調査では、白黒はっきりしない場面も珍しくありません。
まず、いわゆるつまみ申告と呼ばれるケースについて考えてみましょう。
全く申告しないのは怖いから、目立つ売上の一部だけ申告しておこう。
こうした行為は、少しでも申告しているのだから隠蔽にはならないだろうと考えがちではないでしょうか。
しかし、裁判所の判断は厳しいものでした。
平成6年11月22日の判決では、本当の所得よりもごくわずかな金額しか申告していないケースについて、真実の所得を隠蔽しようという明確な意図があったと認定されています。
中途半端な申告は、残りを隠しているという証拠としてむしろ不利に働いてしまうでしょう。
次に、調査官への虚偽の答弁についても確認しておく必要があります。
帳簿の改ざんなどはしていないけれど、税務調査で調査官から質問されたとき、とっさに嘘をついてしまう。
たとえば、その取引の書類は捨ててしまいましたと答えたが、本当は手元にある、というケースです。
これも非常にリスクの高い行為と言えるでしょう。
事務運営指針では、調査のときに具体的な事実について虚偽の答弁を行い、ほかの状況と合わせて隠蔽や仮装が推認できる場合は、重加算税の対象になりうるとされています。調査官への嘘は、それ自体が調査を妨害するための工作、つまり隠蔽行為の一部とみなされるおそれがあるでしょう。
調査官はどこを見ているのか
調査官が重加算税を認定しようとするとき、彼らが特に注目しているポイントがいくつかあります。
経営者として把握しておけば、日頃の経理体制を見直すきっかけにもなるでしょう。
まず、二重帳簿の存在です。
裏帳簿や、正式な帳簿とは別の売上メモが見つかった場合、言い逃れはほぼできません。
次に、帳簿や書類の隠匿や破棄が挙げられます。
本来あるはずの書類が見当たらないという事実は、隠蔽を示す強力な状況証拠になるでしょう。
また、取引先との口裏合わせも見逃せないリスクです。
調査官は反面調査といって、取引先にも確認に行きます。そこで、相手の会社から頼まれて請求書の日付を変えた、という証言が出れば、それは決定的な証拠になりえるでしょう。
そして、外部からみて明らかに不自然な行動があったかどうかも大きな判断材料です。
資料をわざわざ別の場所に移す、架空の名義を使うなど、不自然な行動はすべてチェックされます。
境界線を越えないために、今日からできること
ここまでお読みいただいて、うっかりミスと重加算税の境界線が少し明確になったのではないでしょうか。
その境界線を一言でまとめるなら、事実をありのままに記録しているか、それとも意図的に手を加えているか、という一点に尽きます。
計算間違いは、修正すれば済む問題です。
しかし、書類の書き換えや証拠の隠匿は、会社の信用そのものを壊してしまいかねません。
もし今、あなたの会社に事実と異なる処理をしている帳簿があるのなら、税務調査が来る前に修正申告を検討してください。
自主的な修正申告であれば、原則として重加算税が課されることはありません。
経営をしていると、税金を少しでも減らしたいという気持ちが出てくるのは自然なことでしょう。
その気持ち自体は、何も悪くありません。
ただ、その一線を越えたとき、待っているのは35%以上の重加算税だけではないことを知っておいてください。
青色申告の承認取り消しや、最悪の場合は刑事罰に発展するおそれもあります。
正しい知識を持って、日々の経理をクリーンに保つこと。
それこそが最も効果的な節税対策であり、最大のリスク管理になるでしょう。