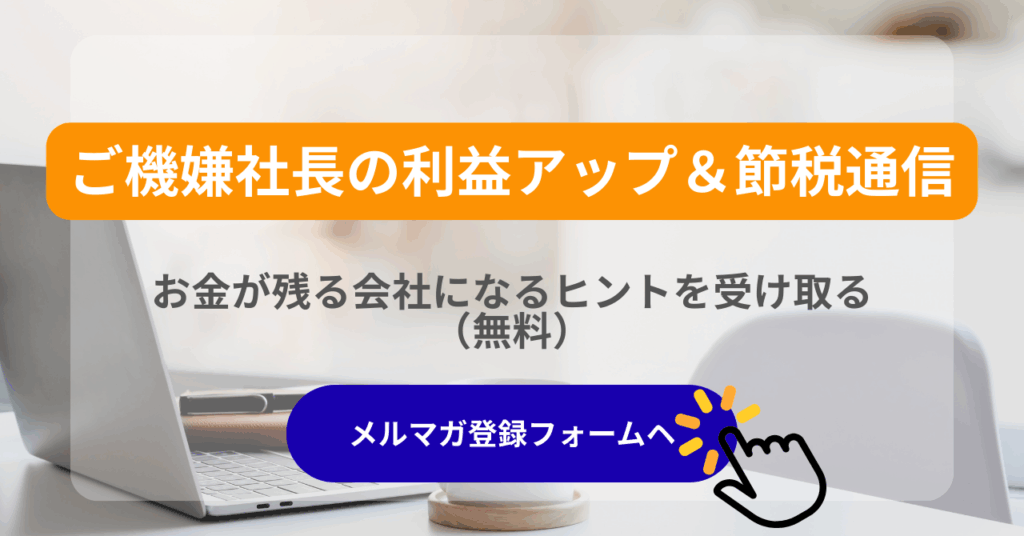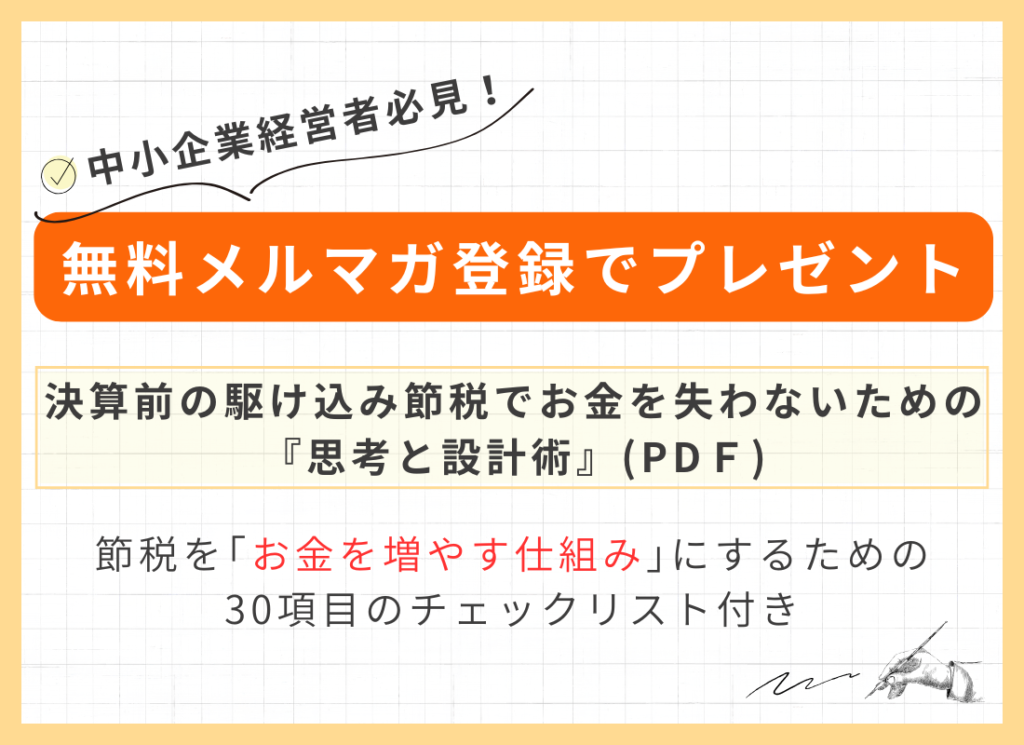交際費の人数をあと2人増やしただけで。会社を危険にさらす重加算税のリスク

こんな場面に心当たりはないでしょうか。
「この飲食代、一人当たりの金額がちょっと超えちゃってますね。参加人数をあと2、3人増やして書類を作っておけば、全額経費で落ちますよ」
あるいは、ご自身でこう考えたことがあるかもしれません。
「昨夜の接待、4人で食べたけど少し高くついたな。人数を7人にしておけば基準内に収まるし、たかだか数万円のことだから大丈夫だろう」
お気持ちはよく分かります。
忙しい毎日の中で、接待のたびに細かい計算をするのは正直面倒ですし、少しの調整くらいどうってことないと感じるのも無理はありません。
でも、ここではっきりお伝えしなくてはなりません。
そのたかだか数万円の安易な工作が、会社に重加算税という致命的なペナルティを招くきっかけになります。
この記事では、多くの経営者が節税テクニックだと思い込んでいる行為が、税務調査の現場でどのように不正と認定されるのかを、実際の事例を交えて解説します。
そもそもなぜ人数のごまかしが起きるのか
まず、この問題が起きる背景にある制度をおさらいしておきましょう。
前提は年間800万円以上交際費を使っている会社とします。
法人税法上の交際費等には、飲食費について一人当たり5,000円(現在は10,000円)以下であれば、交際費等の損金不算入の制限を受けずに全額損金(経費)にできるルールがあります。
この一人当たりという基準がくせ者です。
たとえば、ある接待の飲食代が合計28,000円だったとしましょう。
事実どおりに処理すると、4人での飲食なので一人当たり7,000円になります。
基準額を超えてしまうため、全額を経費にするのは難しくなるでしょう。
一方で、もし7人で飲食したことにすれば、一人当たり4,000円に収まります。
基準額以下になるため、全額経費にできるという計算が成り立ってしまいます。
ここに落とし穴があります。
経営者としては、実際に仕事で使ったお金だし人数を少し調整するくらい誰にも迷惑をかけないだろう、という軽い気持ちかもしれません。
しかし、税務署の調査官にとっては事実の仮装以外の何物でもありません。
税務調査官はここまで見ている
では、税務調査の現場ではどのようにして発覚するのでしょうか。
参加者のリストなんて、それらしい名前を書いておけばバレるはずがない、と思っていませんか?
ここで、ある事例をご紹介します。
ある会社(仮に甲社とします)は、一人当たり5,000円以下の接待飲食費について、法令どおりに参加者名や人数を記載した明細書を作成・保存していました。
書類上は完璧な処理です。
ところが、ある日税務調査が入りました。調査担当の職員は、ある日の飲食代について確認を求めてきます。
甲社の明細書には、飲食代金合計28,000円、参加者7名(一人当たり4,000円)と記載されていました。
これに対し、調査官が取り出したのは、その飲食店のレジシートの写しです。
そこには動かしようのない事実が印字されていました。
レジシートの記載:お通し代 4名分。
調査官はこの矛盾を見逃しません。
「お通しが4つしか出ていないのに、7名で利用されたのですか?」
甲社の担当者は、ここで事情を話すしかありませんでした。
「会議費の予算内に納める必要があったため、参加人数を水増ししました」
なぜ調査官がレジシートを持っていたのか。
それは、税務調査官が甲社が利用した飲食店に対して反面調査を行っていたためです。
反面調査とは、取引先やお店に直接出向いて裏付け資料を集める調査のことです。
経理書類の中に埋もれていたレシートの細部、たとえば客数やドリンクの注文数まで徹底的に分析しているケースもあります。
領収書に印字された合計金額だけを見て安心していませんか?
レジから打ち出される詳細な明細には、ごまかしようのない事実がしっかりと記録されています。
単なる計算ミスではなく、仮装という重い判断が下される
この事例で本当に恐ろしいのは、追徴される税額そのものではありません。
この行為が重加算税の賦課要件を満たすと認定されてしまう点です。
国税通則法第68条では、重加算税の要件として、納税者が税額計算の基礎となる事実の全部または一部を隠ぺいし、または仮装したときと定めています。
では、仮装とは具体的にどういうことを指すのでしょうか。
法律上の定義では、仮装とは、架空契約書の作成や他人名義の利用など、存在しない事実があたかも存在するかのように見せかけることをいいます。
また、事務運営指針では、帳簿書類への虚偽記載や相手方との通謀による虚偽書類の作成を、隠ぺいまたは仮装の典型例として挙げています。
今回の人数水増しを、この定義に照らし合わせてみましょう。
実際には4人しかいなかったのに、7人いたことにして明細書を作成する。
これは、存在しない事実を存在するように見せかけること、そのものです。
さらに、明細書への虚偽記載にも該当します。
つまり、金額が数千円や数万円であっても、やっていることの本質は二重帳簿の作成や架空仕入と同じ、極めて悪質な不正行為とみなされてしまいます。
脱税するつもりがなくても重加算税は課される
経営者の方がよくおっしゃるのが、「悪気はなかった」「脱税しようという気持ちまではなかった」という言葉です。
「担当者は会議費の予算枠に収めるためにやっただけで、脱税をしようとしたわけではないんです」
そうおっしゃりたい気持ちは理解できます。
しかし、裁判例はこの点について非常に厳しい判断を示しています。
最高裁昭和62年5月8日判決では、次のような趣旨が示されました。
重加算税を課すためには、納税者が故意に事実を隠ぺいまたは仮装し、その行為が原因で過少申告になれば、それで十分である。税金を安くしてやろうという明確な認識まで持っていなくてもよい、という考え方です。
つまり、税金を減らそうという明確な意図がなくても、人数を書き換えるという行為を意図的にやった時点で、重加算税の対象になります。
うっかり人数を間違えたなら過失ですが、予算に合わせるために書き換えたなら、それは意図的な行為です。
仮装の事実を作り出すことについて故意や認識があれば、制裁を課す根拠として十分とされています。
重加算税が会社にもたらす3つのダメージ
たかだか飲食費のごまかしで35%の重加算税を課される。
まあ勉強代として払えばいいか、と思われるかもしれません。
しかし、ダメージはそれだけにとどまりません。
1つ目:税務署からの信用を失うこと
一度でも重加算税が認定されると、税務署の管理システムに不正を行った納税者として記録が残ります。
以降数年間にわたって税務調査の頻度が高まり、その内容もより厳しいものになるでしょう。
さらに、過去5年以内に重加算税を課された実績がある場合、次に不正が見つかると税率がさらに10%加重されます。
最大で45%から50%ものペナルティに膨れ上がることもあります。
2つ目:調査が長期化し範囲が一気に広がること
飲食費の人数をごまかす会社だと認定された瞬間、調査官の頭にはこんな考えが浮かびます。
「こんな単純な工作をする会社なら、売上の除外や架空人件費の計上など、もっと大きな不正もやっているに違いない」と。
たった一枚のレシートに端を発した問題が、会社全体の徹底的な洗い出しを招くことになります。
反面調査や銀行調査が行われ、あらゆる書類がチェックの対象となるでしょう。
悪質な不正行為とみなされた場合は、通常の調査期間である3年から5年を超えて、過去7年間まで遡って追徴課税されるリスクも出てきます。
3つ目:金融機関との関係が悪化すること
修正申告書の内容は決算書などを通じて金融機関の目に触れることがあります。
コンプライアンスに問題がある会社と見なされれば、融資の審査に大きな悪影響を及ぼしかねません。
今からでもできること。自主的な修正申告という選択肢
ここまで読んで、ドキッとされた方もいらっしゃるかもしれません。
でも、安心してください。今すぐできる対策があります。
もし、社内でこういった処理が行われているのであれば、まず今日からやめてください。
そして、過去にそういった処理をしてしまっている場合は、税務調査が入る前に自主的な修正申告を行うことをお勧めします。
ここが大事なポイントです。
税務調査の実地調査(臨場)が開始される前に自主的な修正申告を行えば、当初申告に隠ぺい・仮装があった場合でも重加算税は課されません(ただし、調査通知後の場合は過少申告加算税5%が課されます)。
税務調査で指摘されてから慌てて修正するのと、自ら誤りに気づいて修正するのとでは、結果がまるで違います。
行動するなら、早ければ早いほど有利になるでしょう。
クリーンな経営こそが最強の防衛策です
みんなやっているから、少額だから。
そんな軽い気持ちで行った人数の書き換えや宛名の書き換えが、税務調査の現場では事実の仮装という重い不正行為として扱われます。
この記事を通じて、その現実を感じていただけたのではないでしょうか。
重加算税は、悪質な納税義務違反に対する経済的制裁です。
バレなきゃいい、ではなく、バレたら取り返しがつかない。
それが交際費のごまかしに潜む本当のリスクです。
小手先の節税で得られる数万円のキャッシュと、会社が失う社会的信用。
天秤にかけるまでもなく、答えは明らかです。
正しい知識と倫理観を持ち、誠実に申告すること。
それこそが、あなたの会社を無用なトラブルから守る最強の盾になります。