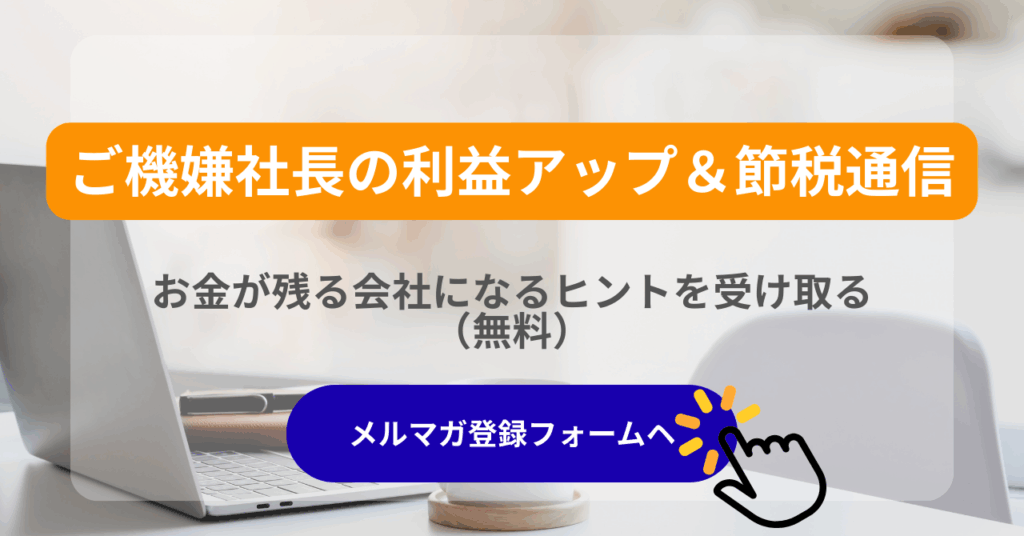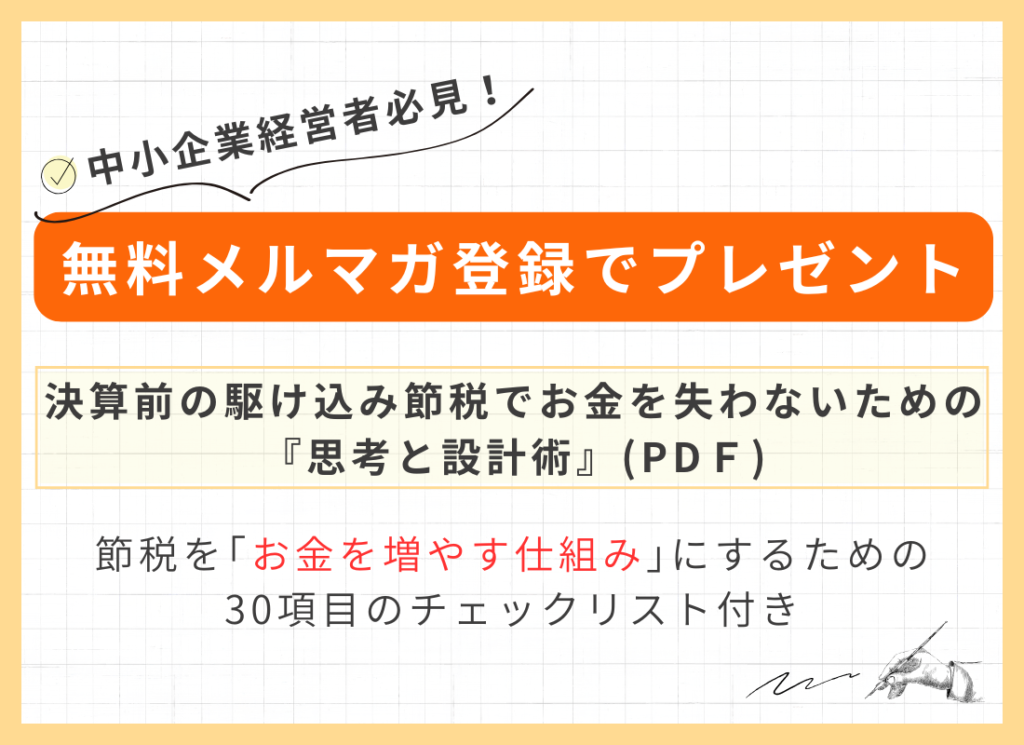社長の退職金は「最強の節税装置」。数千万円単位で手取りが変わる出口戦略の描き方

「引退するとき、会社にいくらお金が残っていればいいですか?」
この質問に、すぐ答えられる経営者は意外と少ないものです。
日々の売上や資金繰りに追われていると、10年後、20年後の自分の姿まではなかなか考えられませんよね。
会社を経営するゴールは、事業を継続させることだけではありません。
創業者であるあなた自身が、十分な資産を持ってリタイアし、穏やかな老後を迎えることも、立派な経営目標の一つです。
そのゴールを実現するための切り札となるのが、役員退職金という制度です。
役員退職金は単なる慰労金ではありません。
税制上、他のあらゆる所得と比べても圧倒的に優遇された、経営者のための特別な受け取り方といえます。
今回は、なぜ役員退職金がこれほど有利なのか、そのしくみと手取りを最大化するための具体的な設計方法について、わかりやすくお伝えしていきます。
役員退職金が圧倒的に有利な3つの理由
退職金には、給与にはない3つの税制優遇が用意されています。まずはその内容を順番に見ていきましょう。
理由その1:大きな非課税枠がある
退職金には、勤続年数に応じた非課税枠が設けられています。これを退職所得控除といいます。
計算式は次のとおりです。
勤続20年以下の場合:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続20年を超える場合:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)
たとえば勤続30年の社長であれば、800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円が非課税として差し引かれます。
長く経営を続けるほど、この控除額は大きくなっていきます。
理由その2:課税対象が半分になる
これこそが、退職金が有利といわれる最大のポイントです。
退職所得控除を差し引いた残りの金額に対して、さらに2分の1を掛けてから税率が適用されます。
課税対象が半分になるということは、税負担も大幅に軽くなるということです。
給与所得には、このような優遇措置は一切ありません。
理由その3:他の所得と切り離して計算される
日本の所得税は、収入が増えるほど税率が上がる累進課税のしくみを採用しています。
しかし退職金は、給与や不動産所得などとは合算されません。
退職金だけで独立して税額を計算するため、もともと給与が高い方でも税率が跳ね上がる心配がないのです。
さらに、退職金には社会保険料もかかりません。
手取りを考えるうえで、これも見逃せないメリットといえるでしょう。
数字で見る衝撃の差額
言葉だけでは実感がわきにくいかもしれません。
具体的な数字で比較してみましょう。
勤続30年の社長が、会社から1億円を受け取るケースを想定します。
役員退職金として1億円を受け取った場合
まず退職所得控除の1,500万円を差し引きます。残りの8,500万円を2分の1にすると、課税対象額は4,250万円になります。
この金額に対して税率が適用されるため、所得税と住民税を合わせても約1,800万円程度で済みます。
結果として、手取りは約8,200万円となります。
社会保険料の負担ゼロで、税負担率はわずか18パーセント程度です。
税務署に否認されないための適正額の考え方
これほど有利な制度であれば、引退時に会社の現金をすべて退職金として受け取りたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし当然ながら、税務署はしっかりとチェックしています。
不相当に高額と判断された部分は、会社の経費として認められません。
では、いくらまでなら適正と認められるのでしょうか。
実務上は功績倍率法と呼ばれる計算方法が広く使われています。
適正額の計算式は次のとおりです。
最終役員報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
最終役員報酬月額とは、引退時の月給のことです。
役員在任年数は役員を務めた期間を指し、功績倍率は社長の場合で2.0倍から3.0倍が一般的な目安となっています。
見落としがちな落とし穴
ここで重要な落とし穴があります。それは最終役員報酬月額の設定です。
節税を意識するあまり、自分の給料を極端に低く設定している社長は少なくありません。
あなたの周りにも、そういった方はいらっしゃいませんか?
しかし、この判断が退職金に大きな影響を及ぼすことがあるのです。
たとえば退職時に月給50万円で役員を30年勤め、功績倍率を3.0倍としても、適正額は4,500万円にとどまります。
これ以上の金額を支給すると、否認されるリスクが高まってしまいます。
一方、月給200万円に設定していた場合はどうでしょうか。
適正額は1億8,000万円まで広がります。
退職間際に慌てて月給を引き上げても間に合いません。
退職までの役員報酬をどう設定するかは、退職金上限額に直結しているのです。
目先の社会保険料を抑えたいという理由で報酬を下げすぎると、最終的な出口で損をしてしまう可能性があります。
知っておきたい5年ルール
これから役員になる方や、分社化で新たに役員に就任したばかりの方は、ぜひ覚えておいていただきたいルールがあります。
役員としての勤続年数が5年以下の場合、2分の1課税の特例は適用されません。
これは特定役員退職手当等と呼ばれるもので、短期間で退職する役員が退職金を使って租税回避することを防ぐための規定です。
この場合、控除額を差し引いた金額がそのまま課税対象となります。
もしM&Aや体調不良などの事情で、就任から5年以内に退職することになった場合、予定していた手取りが大きく減ってしまう可能性があるでしょう。
最低でも6年目に入るまでは役員を続けるという期間管理も、大切な税務戦略の一つです。
退職金の原資をどう準備するか
制度上の適正額が決まっても、肝心の現金が会社になければ退職金は払えません。
1億円の退職金を支給するには、1億円のキャッシュが必要になります。
赤字決算にしてでも借入金で払えばいいと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、退職金の支給で発生した大きな赤字も、繰越欠損金の期限である10年以内に黒字で相殺できなければ、その節税メリットは無駄になってしまいます。
保険に頼りすぎないことも大切
かつては全額損金になる保険で退職金を積み立てる方法が流行しました。
しかし現在は規制が強化されており、以前ほど有利ではなくなっています。
節税目的の保険は、解約返戻金のピーク時期の管理が難しく、資金が長期間にわたってロックされてしまいます。
経営の自由度を奪うリスクもあるため、慎重に検討する必要があるでしょう。
退職金の原資は、特別な金融商品で作るものではありません。
毎期、本業でしっかりと利益を出し、税金を納めて内部留保を積み上げ、手元資金を厚くしておく。
これが最も確実で、最も自由度の高い準備方法です。
今のお金と将来のお金の価値は違う
退職金に回すということは、お金の受け取りを将来に先送りする行為でもあります。
現役時代の1,000万円と、20年後の1,000万円は同じ価値ではありません。
インフレによって貨幣価値が下がっているかもしれませんし、何より若いうちにお金を使って得られる経験や投資機会を逃すことにもなります。
とにかく全額を退職金に回せば得だと単純に考えるのではなく、今いくら必要で将来いくら必要かというライフプランに基づいて、役員報酬と退職金のバランスを設計することが重要です。
あなたは、ご自身の10年後、20年後の姿をどのくらい具体的にイメージできていますか?
出口戦略は今この瞬間に設計するもの
社長の退職金は、単なるご褒美ではありません。
それは、人生をかけて育ててきた会社から、最後に最大の成果を受け取るための大切な仕上げです。
しかし、その成果を最大化するためには、長い時間をかけた設計が必要になります。
具体的には、次のようなステップで考えていきましょう。
まず、いつ引退するかというゴールを設定します。
次に、引退時に必要な手取り額を計算し、そこから逆算して適正な役員報酬月額を決めていきます。
毎期しっかりと利益を出して現金を積み上げながら、税制改正の動向をウォッチし、5年ルールなどの落とし穴を避けることも忘れてはいけません。
これらは、引退直前に慌てて取り組めることではありません。
出口戦略とは、引退するときに考えるものではなく、現役でバリバリ働いているこの瞬間に設計するものです。