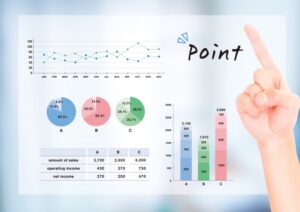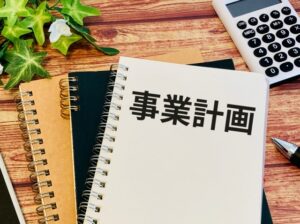あなたから買いたい、をどう計画に落とし込むか?:共感設計と事業計画の関係

「なぜこの人から買いたくなるのか?」という視点
お客様が最終的に「買う」決断をするとき、
価格やスペック以上に影響するのが感情=共感です。
「この人、信用できそう」
「自分のことを理解してくれている感じがする」
「応援したい」
こうした気持ちが働いた瞬間、多少高くても、他社より機能が劣っていても、“あなたから”買いたいと思ってもらえます。
しかし、ほとんどの事業計画書にはこの“共感の設計”が入っていません。
ですが、ここを計画の段階から意識しておくことで、
価格競争や無理な営業に頼らない経営が可能になります。
共感は「感動」ではなく「安心」である
共感とは、感動させることではありません。
もっと地に足のついた、「この人は信じられる」「合ってる」と感じさせる心理的な安心感の構築です。
中小企業にとって、この安心感の設計は資本力や知名度を超える最大の武器になります。
なぜ“共感の設計”が事業計画に必要なのか?
① 売れ続ける理由になる
「なぜこの商品が選ばれているのか?」
それが価格や機能だけだと、より安い/高機能な商品が出れば終わりです。
でも、「あなただから買っている」という理由は、競合に奪われない無形資産になります。
② 営業・広告コストを減らせる
「◯◯さんがいるから、またお願いしたい」
「紹介されて安心できたから、即決した」
こうした声が生まれるのは、事前に“共感が設計されている”からです。
結果として、広告に頼らず集客できる状態=信用資産経営が可能になります。
事業計画に共感を組み込むための3つの戦略
1. 自社の「W字ストーリー」を明文化する
人が最も共感するのは、“強み”と“挫折”が共存しているストーリーです。
これをW字構造で言語化することで、「この人なら任せたい」と思ってもらえる確率が格段に上がります。
例:W字ストーリー構成
- 起点(過去の原体験)
- 成功体験(前向きな挑戦)
- 挫折や困難(落ちる部分)
- それを乗り越えた工夫や学び
- 今の提供価値にどう繋がっているか
これを事業計画書の自己紹介や創業背景パートに必ず入れることで、共感が土台になります。
2. 顧客の「5つの欲求」に対応する設計
心理学者ウィリアム・グラッサー氏の「選択理論」では、人の行動は以下の5つの欲求で動くとされています。
| 欲求 | 内容 | 設計例 |
|---|---|---|
| 愛・所属 | 誰かと繋がっていたい | コミュニティ、会員制、紹介制度 |
| 力・価値 | 認められたい | SNSでの紹介、成功事例の紹介 |
| 楽しみ | ワクワクしたい | イベント開催、限定特典 |
| 自由 | 自分で選びたい | プラン選択制、カスタマイズ可 |
| 安全・安心 | 不安なく利用したい | 顧客対応の見える化、手厚いサポート |
この5つの視点をサービス設計やマーケティング戦略に盛り込むことで、「なんとなく好き」「応援したい」という共感が生まれます。
3. CAP戦略で「共感→信頼→購入」の導線を設計
事業計画の中で、情報発信戦略を「CAP」の流れで組み立てると、自然な共感導線が作れます。
| フェーズ | 意味 | 共感の役割 |
|---|---|---|
| C(Connect) | 繋がる | SNS・紹介・地域活動で接点を持つ |
| A(Archive) | 蓄積する | 過去実績やストーリーをブログ/動画に残す |
| P(Push) | 投げかける | 最新情報を発信し、存在を思い出してもらう |
この3段階を年間計画や発信スケジュールに組み込むことが、見えない資産=共感力の積み上げに繋がります。
共感は「後づけ」ではなく「最初から組み込む」
「発信に困ってます」
「何を書いたらいいか分からない」
という経営者ほど、“何を伝えるか”を事業計画に組み込んでいないことが多いです。
商品だけで勝負するのではなく、
“人”として選ばれる設計を、最初から組み込んでおくことが、価格競争を超える最大の策です。
まとめ:事業計画に共感の設計図を
- ストーリー(W字構造)を明文化し
- 欲求に対応するサービス構成を作り
- 接点〜発信〜信頼の流れ(CAP)を事前に設計する
この3つを事業計画に落とし込めば、
あなたのビジネスは“価格や機能では比較されない”領域に到達できます。
今すぐできる行動
- 自分の人生・事業の「W字ストーリー」を紙に書き出す
- 自社商品が満たしている「5つの欲求」を整理する
- 発信計画を「CAP」に基づいて組み立ててみる