【経営者必読】電子帳簿保存法の実務とリスク~法改正と対応の盲点を読み解く~
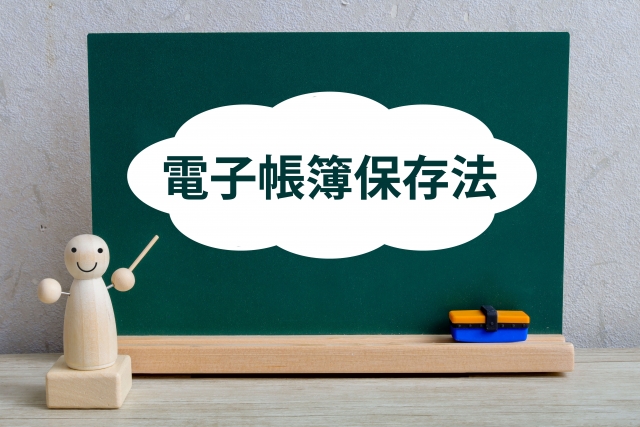
会社の帳簿書類管理は、かつては紙が当たり前でした。しかし、社会全体がデジタル化へと移行する中、帳簿や請求書の保存にも新しい「法的常識」が求められるようになりました。その中心にあるのが「電子帳簿保存法」です。
この法律は、単に紙の代わりにデジタルで保存してよいという許可の法律ではなく、適切な手続と管理体制を前提とした義務化の法律へと進化しています。とりわけ2024年の法改正以降、経営層がこの問題を無視することは、企業リスクの放置と同義といっても過言ではありません。
本記事では、電子帳簿保存法の基礎から、最新の制度変更、そして実務上の落とし穴を、経営者視点でわかりやすく整理します。
電子帳簿保存法とは何か? ― 紙の時代から「証明できるデータ保存」へ
電子帳簿保存法(電帳法)は、1998年に施行された税法上の特例法です。
当初は、「紙でなければならない」とされていた帳簿や決算資料、領収書などの税務関係書類を電子での保存も認める目的で制定されました。
重要なのは、電子保存が「簡易な運用で済む」という意味ではない点です。むしろ、電子という改ざん・削除が容易な形式だからこそ、紙以上に厳密な要件が求められる法律なのです。
対象となる保存形態は大きく分けて以下の3分類です。
- 電子帳簿等保存:最初から電子で作成した帳簿・仕訳帳・試算表などを保存する場合
- スキャナ保存:紙で受領・作成した書類をスキャナ等で読み取り、電子で保存する場合
- 電子取引データ保存:メールやWeb経由で受け取った請求書・領収書等の電子データを保存する場合
これらの保存には、それぞれ異なる技術的・管理的要件が課されており、「とりあえずPDFで残しておけばOK」という考え方は、現行法では完全に通用しません。
2024年改正:電子取引データの紙保存は原則「違法」に
もっとも注目すべき法改正が、2024年1月から義務化された電子取引データの保存要件です。
これにより、メール添付の請求書やクラウド請求書など、電子で授受した取引データは、電子のまま保存しなければならないというルールが法的に確定されました。
✅ ポイントは以下の3点:
- 紙に印刷して保存するだけでは違反(電子データを削除するのはNG)
- 要件に適合しない保存方法は青色申告の取消対象になる
- 重加算税(最大50%)など、ペナルティを受けたときの損失が大きい
対象となる「電子取引」の具体例:
- 請求書をPDFでメール受信した
- 領収書をオンライン決済後に自動発行された
- 契約書を電子契約サービスで締結した
- サービス利用明細がクラウド上に発行された
これらは、もはや「紙に出力してファイリングする」だけでは保存義務を果たしたとはみなされません。電子で来たものは電子で保管するのが基本原則です。
電子保存の基本要件:真実性・可視性・検索性をどう確保するか
電子帳簿保存法の本質は、保存方法ではなく、保存されたデータの信頼性と検証可能性にあります。形式を整えるだけでは不十分で、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります:
真実性の確保
→ データの改ざんや後日編集を防ぐための仕組みが必要
主な方法:
- タイムスタンプの付与
- データ改ざん検知機能付きクラウドシステムの使用
可視性の確保
→ 税務調査や社内確認時に、速やかに表示・印刷が可能であること
主な方法:
- 一般的な閲覧ソフトで読めるファイル形式(PDFなど)
- モニター表示・帳票出力が即時できる環境の整備
検索性の確保
→ 日付、金額、取引先などの基本情報をもとに、特定のファイルを即座に抽出可能であること
主な方法:
- ファイル名の命名ルールの統一(例:取引日・相手先・金額の入力)
- 検索機能付きのクラウド保管システムの導入
これらの条件を満たしていない場合、形式的に保存していたとしても、税務上は「保存していない」と評価される可能性があります。
実務現場での見落としと典型的ミスパターン
企業の現場では、次のようなミスが非常に多く発生しており、帳簿保存義務違反となる可能性が高いため注意が必要です。
✖ タイムスタンプ未対応
電子請求書をPDFで保存していても、改ざん防止の対策を講じていないと要件を満たしません。
✖ バラバラなファイル保管
クラウドやローカルサーバーに整理されていない状態で保存している場合、検索性が確保できず違反です。
✖ 紙保存に頼り、電子データを削除
電子で受領した請求書を印刷しただけで電子データを削除してしまう行為は、2024年以降は明確な保存義務違反になります。
企業が構築すべき体制とシステム
電子帳簿保存の実務は、経理部門だけの課題ではありません。情報システム部門、営業部門、総務部門なども関与する全社横断の体制を構築する必要があります。
✅ 対応する主なシステム:
- クラウド型の書類管理・会計システム(例:freee、マネーフォワード、楽楽精算など)
- タイムスタンプ・電子署名対応の保管システム(例:DocuWorks、DocuSign、Shachihata Cloudなど)
- 内部マニュアルと社員教育の徹底(導入後放置せず、定期的に運用状況を確認)
さらに、定期的に保存状態をチェックし、現場でルールが守られているかどうか、抜き打ちで検証するような体制も有効です。
結論:電子帳簿保存法は単なるIT対応ではない──経営の信頼性を守る法対応
電子帳簿保存法の目的は、形式的な保存義務の履行にとどまりません。「いつ、誰が、どのような取引を、何の根拠に基づいて行ったのか」を証明する、企業の透明性の根幹を支える仕組みです。
税務リスクを未然に防ぎ、金融機関・取引先からの信頼を守るためには、保存体制を見直し、法令準拠を経営戦略の一部として位置づけることが必要です。







