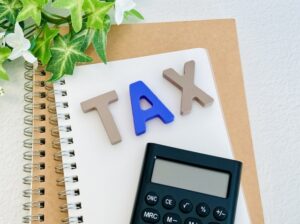意思決定の落とし穴は税金にも影響する:手元にお金を残すための思考法

中小企業の経営者の皆さん、「売上は増えているのに、なぜかお金が残らない」と感じたことはありませんか?
この悩み、実は多くの経営者が抱えており、その原因の多くが「目に見えにくい判断ミス」に潜んでいます。そしてこの判断ミス、つまり意思決定の落とし穴が、節税やお金の残り方にまで大きく影響してくるのです。
私は税理士として多くの企業を見てきましたが、「税金対策」と「利益を残す仕組み」は、単なるテクニックではなく、思考のクセの見直しから始まると実感しています。
本記事では、売上は上がっているのにお金が残らない原因を、「意思決定の罠」と「節税思考」の視点から掘り下げ、改善策をご提案します。
誤った判断が招く「ムダな納税」
たとえば「埋没費用」にとらわれて、もう償却が終わった機材を高い維持費で使い続けていたりしませんか?
これは「もったいない」という感情に引っ張られた結果ですが、税務的には非効率。
維持費や管理コストが経費としてかさむだけでなく、新しい投資のタイミングを逃す原因にもなります。
また「ハロー効果」、つまり相手の一部の印象で全体を評価してしまう心理も、危険な判断ミスを生みます。
よくあるのが「大手だから安心」とコンサルティング会社に依頼し、実は内容が自社にまったく合っていない高額サービスにお金をつぎ込んでしまうケースです。
こうしたムダな支出は、利益を圧迫し、当然税金面でも不利になります。
計画錯誤と節税のタイミングのズレ
「今年は計画的に節税しよう」と思っていても、毎年ギリギリになってから慌てて経費を使い始めたりしていませんか? これは「計画錯誤(planning fallacy)」というバイアスの影響です。
「時間はまだある」と楽観的に判断し、実際にはタイミングを逃して必要な節税策が取れなくなる。
たとえば、決算前の棚卸資産の調整、決算後の役員報酬の見直し、生命保険などの導入、全て“間に合わなかった”というケースは少なくありません。
これは単に「忙しかったから」ではなく、意思決定の初動が遅れていたことに根本原因があります。
思い込みが生む「不要な支出」と「機会損失」
「この制度はうちには使えない」と最初から思い込んで、助成金や税額控除などの有利な制度を使っていない経営者も多く見かけます。
これは典型的な「トンネルビジョン(視野狭窄)」です。税務の世界には「知らないだけで損をしている制度」が山ほどあります。
たとえば、事業承継税制や中小企業投資促進税制、賃上げ促進税制などは、適用できれば大きな減税が可能です。
こうした制度は一見複雑に見えますが、税理士に相談すれば活用できる余地があるかもしれません。
思考モデルの更新が利益構造を変える
思考モデルとは、物事をどう捉えて判断するかの「頭の中の設計図」のようなものです。この設計図が古いままだと、利益が残らない構造から抜け出せません。
たとえば「節税=経費を増やすこと」と考えている人が多いですが、これは非常に危険な思考です。
本当に目指すべきは、「無駄な税金を減らしつつ、手元に現金を残すこと」。そのためには、「キャッシュフローを改善するための投資」や、「将来の利益を生み出す経費」こそが重要です。
決算前にやるべき意思決定プロセスとは
私が経営者の方にお勧めしているのは、「意思決定日誌」と「税理士との事前打ち合わせ」です。
意思決定日誌とは、いつ・なぜ・どんな判断をしたかを記録しておくメモです。これがあるだけで、後になって「なんでこの支出をしたのか」といった後悔が減ります。
また、決算2〜3ヶ月前には、税理士と以下のような点をすり合わせましょう:
- 来期の見通しと利益計画
- 節税策の選択肢(保険、退職金、固定資産など)
- 助成金や優遇税制の活用可否
- 資金繰り表と納税予定額の確認
このように、「先手先手」で意思決定を行うことで、不要な支出を防ぎ、税金の支払いも最適化できます。
まとめ:冷静な思考とシンプルな仕組みがキャッシュを守る
売上を上げるのは素晴らしいことです。しかし、それが「税金で消える構造」になっていたら本末転倒です。
必要なのは、冷静な意思決定と、それを支えるシンプルな思考の枠組み。今回ご紹介した内容を実践していけば、ムダな出費を減らし、無駄な納税を抑え、利益を「残す」経営が実現できます。
そして、最も大切なのは「感情に振り回されず、数値と論理に基づいて判断する習慣」です。
税金も、経営も、「思い込み」ではなく「見える化」と「仕組み化」で大きく変わります。