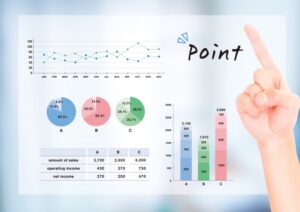先延ばし癖のある経営者ほど行動を強制する“構造的事業計画”が必要です
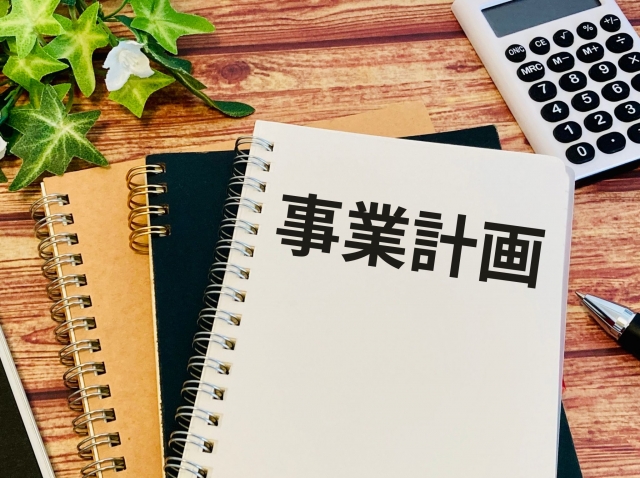
「やらなきゃいけないのは分かってるんだけど…」という状態
中小企業の経営者は日々忙しく、
経営改善・販促計画・コスト見直しなど、
「やるべきと分かっていること」がたくさんあると思います。
でも、こうしたタスクは後回しになりがちです。
その理由は単純です。
めんどくさいし、成果がすぐ出ないから。
経営者といえど人間。自制心には限界があります。
だからこそ、意思や気合いに頼らない、“行動せざるを得ない”事業計画=構造的事業計画が必要なのです。
行動を止める“3つの壁”とその正体
経営課題が「分かっていても動けない」理由は、以下の3つに集約できます。
① 不快感:やりたくない・面倒
利益率の見直し、原価計算、営業トークの見直しなど、
脳が「今やりたくない」と判断すると、先延ばしになります。
② 不確実性:どうやるか分からない
手順が曖昧なタスクは、脳が危険と判断して行動を止めようとします。
「どこから手をつけていいか分からない」という声が多いのはこのため。
③ 即効性のなさ:成果がすぐ出ない
“明日の売上”には関係ないことに、モチベーションが湧かない。
結果、広告や営業など短期施策ばかりを優先してしまう。
気合では突破できない。だから“仕組み”で動く
「やらなきゃ」と思い続けるほど、
罪悪感が蓄積して余計に動けなくなります。
だから必要なのは、意志の力を必要としない“行動を促す設計”です。
事業計画の中に「やらないと進まない仕組み=強制装置」を入れておくのです。
構造的に行動できる事業計画とは?
以下の3つを組み込んでいるかどうかが鍵です。
1. 行動KPI(数値化された行動目標)があるか?
売上目標だけでなく、行動の目標を明文化しておきます。
| 行動 | 頻度 | 目的 |
|---|---|---|
| 顧客リストにDM送付 | 月1回 | 継続接点の維持 |
| ブログ更新 | 月4回 | 信頼資産の蓄積 |
| 原価率の確認 | 月1回 | 利益率改善 |
売上は結果でしかありません。
それを生む行動そのものをKPI化し、事業計画に記載することが不可欠です。
2. 外圧設計:外からの締切や評価を組み込んでいるか?
自分だけのルールは破られます。
でも、「他人に提出」「報告」「評価される」となると、脳は“やらざるを得ない”と感じます。
実践アイデア:
- コンサルや税理士に月1回レポート提出
- 顧客向けに毎月コンテンツ発信(カレンダー化)
- 社員に毎週「今週やったこと」を報告してもらい、自分も同じく提出
→「やらないと困る仕組み」を作ることが最大のモチベーションです。
3. パッケージ化とスケジュール化で先延ばしを潰す
タスクが複雑であるほど、人は動けなくなります。
そこで事業計画に、あらかじめ“定形パッケージ”として業務を組み込んでおくことが有効です。
例:飲食店の販促施策
| 月 | 定型販促 | 実施理由 |
|---|---|---|
| 1月 | 新年企画DM | 年始のご挨拶と再来店促進 |
| 2月 | バレンタイン限定メニュー | 話題性のある集客 |
| 3月 | ホワイトデーイベント | 来店リピート |
→ 毎月の販促が「考えてから動く」ではなく「決まってるから動く」状態に。
「未来の自分を信用しない」ことが、最高の計画
多くの人がやりがちなのが、
「来月やろう」「時間ができたらやろう」という未来依存です。
でも未来の自分は、今と同じように迷って疲れて後回しにします。
だからこそ、「いま意思決定して、未来の自分が迷わず動けるように設計しておく*のが事業計画の本質です。
まとめ:「仕組みで動く人」になるための事業計画
- やるべきことを「気合い」に頼らない
- 毎月やることが“決まっている”状態にする
- 他人に見せる/報告する“外圧”を組み込む
この3点を盛り込んだ「構造的事業計画」が、あなたの先延ばしを打ち破る最短ルートです。
今すぐできる行動
- 自分の「行動KPI」を月単位で3つ書き出す
- それを「誰に提出するか」を決める(外圧設計)
- 業務をテンプレート化して、スケジュールに組み込む