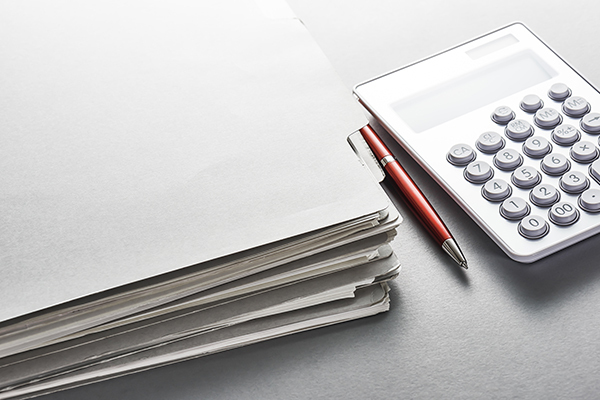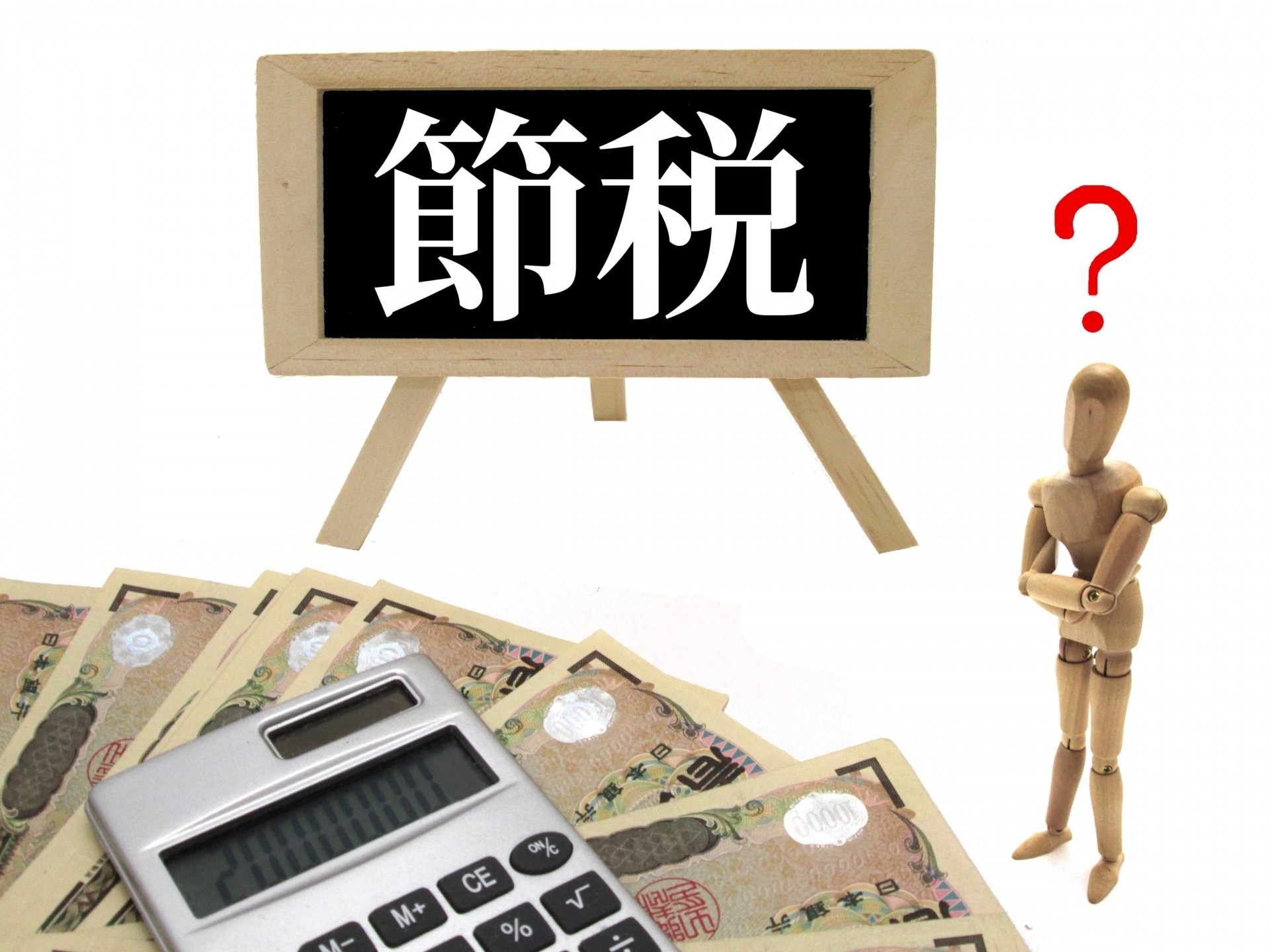
決算賞与は法人税の節税につながる?節税効果と活用のポイントを徹底解説
企業が利益の最終調整を図る手段として注目される「決算賞与」。一見すると単なる社員への報酬の一種に思えるかもしれませんが、適切に活用すれば法人税の節税につながる重要な戦略でもあります。
本記事では、決算賞与の基本的な仕組みから節税への具体的な効果、実務上の注意点までを網羅的に解説します。
経営者や経理担当者にとって、判断を誤ると損にも得にもなるこの制度を正しく理解し、自社にとって最適な運用を目指しましょう。
決算賞与とは?通常賞与との違いを整理
決算賞与とは、会社の決算期に合わせて支給される賞与のことです。
その年の業績に応じて支給の有無や金額が決まり、いわば「その年の結果に対するボーナス」としての性格を持ちます。
一方、通常賞与とは夏や冬など定められた時期に定期的に支給される賞与を指します。給与体系に組み込まれているため、業績に関わらず支給されるケースも少なくありません。
このように、決算賞与と通常賞与では「業績との関連性」と「支給のタイミング・ルール」に大きな違いがあります。
決算賞与が法人税の節税に有効な理由
決算賞与が節税に役立つ最大の理由は、「損金算入が可能である」点です。
損金として処理することで、その分当期利益を圧縮でき、結果として法人税の負担を軽減できます。
ただし、支給が翌期になるケースが多いため、損金算入には以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
決算賞与が当期の経費になる3つの条件
-
決算期末までに支給対象者に対し金額を通知していること
-
決算期終了後1ヶ月以内に、通知通りに支給していること
-
通知した金額を当期中に費用として経理処理していること
これらをクリアすれば、実際の支払いが翌期になっても、当期の損金として扱うことが可能です。
実例でわかる節税効果
節税のインパクトをより具体的に理解するため、以下のようなケースでシミュレーションしてみましょう。
-
税引前当期純利益:1500万円
-
決算賞与:300万円
-
法人税等の実効税率:30%
決算賞与を計上しない場合
法人税等の額は以下の通り:
1500万円 × 30% = 450万円
決算賞与を計上した場合
利益が1200万円に圧縮されるため:
(1500万円 - 300万円)× 30% = 360万円
この結果、90万円の節税効果が生まれます。
ただし後述の通り、キャッシュアウトが大きいため、節税額だけで判断するのは危険です。
決算賞与のメリット3選
決算賞与には以下のようなメリットがあります。
1. 法人税等の節税が可能
もっとも実感しやすいのが節税効果です。
決算賞与により利益をコントロールでき、法人税額の調整が可能になります。特に当期利益が想定以上に出てしまった場合に、有効な利益調整手段となります。
2. 従業員のモチベーション向上
「利益が出たから還元する」というスタンスは、社員の納得感とやる気につながります。
業績と報酬が結びつくことで、会社への貢献意識も高まるでしょう。
3. 外部関係者へのアピール効果
決算賞与の支給実績は、「社員への還元を重視する健全な経営」を印象付けます。
株主や取引先への信頼感、人材採用における訴求ポイントとしても有効です。
決算賞与の注意点3つ
効果が大きい分、デメリットやリスクも存在します。以下の3点には特に注意が必要です。
1. キャッシュの流出による資金繰り悪化
先述の例では、決算賞与によって節税額は90万円でしたが、賞与として300万円の支出が必要になります。差額210万円は純粋なキャッシュアウトです。短期的な資金繰りへの影響は必ずチェックしましょう。
2. 決算賞与が常態化すると期待値が上がる
一度でも支給してしまうと、社員の間で「毎年もらえるもの」という認識が定着する恐れがあります。業績悪化により支給を取りやめた際、士気の低下や不満の要因になる可能性があります。初めから支給条件を明文化しておくことが重要です。
3. 決算期に事務処理が集中する
賞与額の計算、通知、社会保険・税金の処理、経費計上、支払いまで、短期間に多くのタスクが発生します。特に経理・人事担当者の負担が大きくなる点を見越し、事前準備と分担体制が不可欠です。
まとめ:メリットとリスクを天秤にかけた判断がカギ
決算賞与は、法人税の節税手段として非常に有効な選択肢です。業績を確認したうえで支給額を柔軟に調整できるため、利益コントロールに最適な手段の一つといえるでしょう。
さらに、従業員の士気向上や外部への好印象といった副次的効果も期待できます。
ただし、キャッシュフローの悪化や業務負荷の増大、社員への過度な期待といったリスクも無視できません。
決算賞与を導入・運用する際は、節税効果と経営への影響をトータルで評価し、「本当に自社にとって必要か?」を慎重に判断することが重要です。
最終的には、短期的な節税にとどまらず、長期的に持続可能な制度として設計できるかが、成功と失敗を分けるポイントになるでしょう。