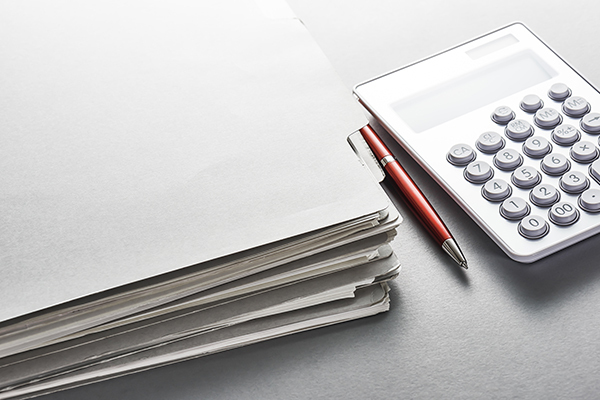「節税・租税回避・脱税」の境界線:正しい納税判断で会社を守るために
会社経営において「納税」は避けて通れないテーマです。利益を上げたい。しかし税金はできる限り抑えたい。これは多くの経営者が抱く自然な思いでしょう。
ですが、そこには常に「どこまでが許されるのか」という、グレーゾーンのリスクがついて回ります。
税金を抑える方法として「節税」という言葉は日常的に使われますが、同じような場面で「租税回避」や「脱税」という言葉も耳にします。
この3つ、実は明確に線引きされるべき行為であり、それぞれに税務上の意味とリスクが異なります。
本記事では、中央大学教授・酒井克彦氏が著書『スタートアップ租税法(第3版)』で紹介している「本屋の立ち読み」のたとえ話を借りながら、節税・租税回避・脱税の違いを明確にし、経営者が知っておくべき納税判断の基準と税務リスクへの備えについて解説します。
1. 「白・グレー・黒」――3つの税務行為の分類
まずは大前提となるイメージから掴んでいきましょう。
-
節税は「白」
-
租税回避は「グレー」
-
脱税は「黒」
このように3つの行為は、その「合法性」と「税務上のリスク」に応じて色分けされます。
「白」と「黒」は誰の目にも比較的はっきりしています。しかし問題は「グレー」です。グレーにも白寄りのグレーから、ほぼ黒に近いグレーまで幅が広く、一概に「セーフ」とも「アウト」とも判断しづらい領域です。
税務の現場では、このグレーの濃淡が最大の争点になります。そしてこの濃さを冷静に見極め、経営者を正しい方向へ導くことが、税理士の重要な役割です。
2. 節税とは何か? ― 正々堂々とした税負担の軽減策
「節税」とは、税法のルールに従って合法的に税金を減らす行為です。
酒井教授のたとえ話によると、これは「立ち読み禁止」と書かれている本屋で、本を買う予定の人がレジで会計を待ちながら立ち読みしている状態です。
つまり、店長(=税務当局)が許した範囲で行動しているので、問題はありません。
税法的に言えば、「租税法規が予定しているところに従って税負担の減少を図る行為」です。
たとえば次のような施策は、完全に節税の範疇です:
-
各種優遇税制(中小企業投資促進税制、賃上げ促進税制など)の適用
-
会議費や出張手当など、要件を満たした支出の経費処理
-
少額減価償却資産の特例の活用
これらは、要件さえクリアしていれば認められる「納税者の権利」です。行使しない手はありません。
ただし、使わなければ自動で税務署が教えてくれるわけでもありません。
本屋の店長が「レジ待ち中の立ち読みどうぞ」と勧めてくることがないのと同じです。
3. 租税回避とは何か? ― グレーゾーンの賭けに近い行為
「租税回避」は、税法の抜け穴をついて税金を減らそうとする行為です。一見すると違法ではありません。しかし、税務当局に否認されるリスクが高く、実質的には非常に不安定な立場です。
たとえば、次のような行為が租税回避とされる可能性があります:
-
海外に形式上だけの子会社を設け、利益を移す
-
所得を意図的に家族や別法人に分散させる
-
ファンドや匿名組合を利用し、課税ベースを圧縮する
本屋のたとえでは「レジの周りで買う気もないのに立ち読みする」「立ち読みが禁止されているので座って読む」といった行動にあたります。
これが許されるかどうかは、以下の二つの原則のどちらに立脚するかで変わります:
-
租税法律主義:「ルールに書かれていなければ課税できない」
-
租税公平主義:「常識的に見て不公平なら課税していい」
税務調査や訴訟で争われるケースの多くが、このどちらの原則に基づくべきかという点に集約されます。
結局のところ、租税回避は「法の抜け穴をついた行為」であり、それが許されるか否かは、ケースバイケースでの解釈・判断に委ねられます。だからこそリスクは高く、慎重な検討が求められます。
4. 脱税とは何か? ― ルール違反の確信犯
最後に「脱税」です。これは明確な違法行為であり、重いペナルティの対象になります。
たとえば、
-
売上を意図的に隠す
-
架空の経費を計上する
-
請求書を偽造する
-
海外口座に資金を隠す
こうした行為は「仮装」「隠ぺい」と呼ばれ、悪質性が高いと判断された場合には「重加算税」の対象となり、経営者が刑事責任を問われることさえあります。
本屋の例でいえば「本棚の裏で隠れて読む」行為です。誰がどう見てもアウトです。
さらに注意すべきなのは、「過失によるミス」と「故意による脱税」はまったく違うという点です。
たとえば:
-
経理ミスで売上の一部が計上されていなかった(→ 過失)ミス
-
架空の請求書で経費を水増しした(→ 仮装)故意
-
売上を抜いて別口座にプールしていた(→ 隠ぺい)故意
このように、脱税と認定されるかどうかは、「故意」があったか否かがカギとなります。
5. 税理士の役割は「盾」
顧問税理士は、税務の専門家であると同時に、会社を守る盾でもあります。税務調査の際、交渉の矢面に立ち、経営者の判断が正しかったことを主張するのも税理士の仕事です。
しかし、税理士のアドバイスも万能ではありません。裁判事例や最新の税務通達をもとに組み立てた意見であっても、税務当局や裁判所に否認されることもあります。
だからこそ、経営者自身が白・グレー・黒の感覚を理解し、自らの頭で「その節税策は本当に白なのか?」「グレーの中でも黒寄りではないか?」と考える視点を持っておく必要があります。
まとめ:正しい判断で、会社の未来を守る
節税・租税回避・脱税――この三者の違いは、時に紙一重にも見えます。しかし、実際には大きな違いがあります。知らずに越えてしまった一線が、取り返しのつかない事態を招くこともあります。
大切なのは、「税金を抑えること」よりも、「その手段が正当であること」。それが結果的に、会社を守り、経営の自由度を高め、社会的信用を築くことにつながります。
そしてそのためには、顧問税理士と信頼関係を築きながら、会社としての「税務方針」を明確にし、一貫した判断基準を持つことが何よりも重要です。
経営者が主体的に税務に向き合う。それが、強い企業への第一歩です。