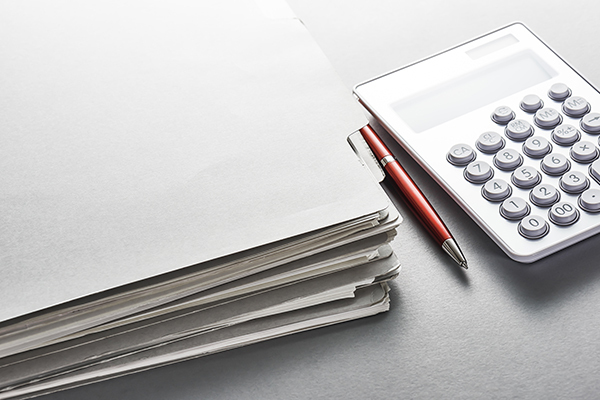経営者のための「本当に意味のある節税」5つの視点
企業が利益を上げれば、当然ながら税金も発生します。これは日本の租税制度における基本的なルールであり、避けて通ることはできません。しかし、利益の多くを税金で消耗するのではなく、なるべく手元に残し、次の投資や企業体力の強化に回したいというのは、どの経営者にとっても自然な願望でしょう。
重要なのは、「賢い節税」をすることです。
競合他社と同じ売上・利益であっても、支払う税金の額に大きな差が生じれば、資金力、成長力、投資力において後れを取ることになりかねません。
一方で、「お金が残らない節税」や、「経営の足を引っ張る節税」が存在することも事実です。
目先の税金を減らすために本来必要のない支出をする、制度の趣旨に反した利用で将来に禍根を残すなど。そんな節税は本末転倒です。
そこで本記事では、節税を考えるうえで重要となる5つの視点を紹介します。単なるテクニックではなく、企業の豊かさを高め、持続的な成長に資する視点として、ぜひ参考にしてください。
1. 所得(利益)の「種類」を変える
「所得の種類を変える」とは、同じ金額を受け取るにしても、その性質を変えることによって課税の扱いを変えるという考え方です。日本の税制では、所得の種類ごとに課税方法が異なり、税率や控除の有無も大きく変わります。
たとえば、給与所得と退職所得では、同じ1000万円でも課税される税額はまったく違います。退職所得は税制上かなり優遇されており、長期勤務に対する報酬としての性質を考慮して、課税額が軽減される仕組みです。
日本の所得税には以下の10種類の所得区分があります:
-
利子所得
-
配当所得
-
不動産所得
-
事業所得
-
給与所得
-
退職所得
-
山林所得
-
譲渡所得
-
一時所得
-
雑所得
同じ金額を受け取っても、どの所得区分に属するかによって納税額が大きく異なるのです。
また、財産をお子様に渡す際にも、「労働の対価」として支払えば所得税、「無償」であれば贈与税の対象になります。それぞれの税制の特性とリスクを理解し、どの区分に落とし込むかを慎重に計画すれば、合法的かつ合理的に税負担を軽減できます。
2. 所得(利益)の「帰属」を変える
次に注目すべきは、「誰がその所得を得るのか」、すなわち所得の帰属です。
代表的な例は、個人事業を法人化することです。
個人事業にかかる所得税は超過累進課税であり、所得が増えるほど税率も上がります。一方で、法人税は利益に比例する固定税率(中小法人であれば23.2%以下)を採用しています。
利益がある程度を超えた場合には、法人化した方が全体の納税額を抑えられるのです。
さらに、法人の株主構成を見直すことも節税につながります。一般的に「社長=株主」である中小企業が多いですが、奥様やお子様を株主として加えることで、配当や会社に残る利益の帰属先を分散できます。これにより、将来的な相続財産の圧縮も図れます。
ただし、節税目的だけで名義を借りたり、不適切な名義分散を行うと、税務上否認される可能性もあります。慎重な設計が不可欠です。
3. 所得(利益)の「場所」を変える
グローバル展開が視野に入る企業にとっては、所得の発生する「場所」も重要な節税ポイントになります。
日本は他国に比べて法人税率が高い国の一つです。そのため、海外拠点で利益を出し、国内での利益を抑えることで、全体の納税額を下げる戦略が考えられます。
例えば、税率の低いシンガポールに現地法人を設立し、そこに研究開発やマーケティングといった「高付加価値機能」を移転することで、合理的に利益を移転することができます。
ただし、移転価格税制という国際的な税制ルールがあり、実態の伴わない利益移転は否認される可能性が高いです。現地の実際のリスク負担や機能を適切に考慮し、文書による証明ができる体制を整えておく必要があります。
さらに重要なのは、海外で得た利益を最終的にどうやって日本に戻すかという点です。
配当、ロイヤリティ、役務提供など、送金の形式に応じて課税関係が変わります。税金の発生タイミングと額をコントロールできるよう、利益還流戦略まで含めた設計が不可欠です。
4. 所得(利益)の「時間」を変える
所得の発生する「タイミング」、すなわち税金の支払時期をコントロールすることも、重要な節税策です。
基本的には、納税を将来に先送りすることで、その分の資金を一時的に手元に残し、運用することができます。これにより、資金繰りの安定や次の成長投資に活用する余地が広がります。
しかし、この方法には注意点もあります。
例えば、節税のために不要な設備投資をしてしまうと、資金をロックされるだけでなく、他の有望な投資機会を逃すリスクも高まります。納税の繰延が目的化すると、事業の健全性を損なう危険があります。
理想的には、納税を遅らせることで得られる「資金の運用益」が、それによって失われるリターンやリスクを上回る場合に限り、選択肢として検討すべきです。
5. 優遇税制を活用する
最後に紹介するのは、「優遇税制の活用」です。
これは、その時々の政府の政策方針に応じて制定される特別な税制を、事業戦略と組み合わせて活用するというアプローチです。
具体的には以下のようなものがあります:
-
資産の即時償却(中小企業経営強化税制など)
-
賃上げ促進税制(従業員の給与増加に応じた控除)
-
研究開発税制(試験研究費の一定割合を税額控除)
-
地域振興系の減税(地方拠点強化税制など)
これらの優遇措置は、基本的に事前申請や事前手続きが必要です。
申告期限後に「知っていたら活用できたのに」と悔やんでも後の祭りです。
制度を使いこなすには、日ごろから情報収集を怠らず、投資・雇用・研究開発といった事業活動を「税制面からも設計する視点」が必要になります。
まとめ:節税は目的ではなく「手段」である
節税とは、企業の競争力を高め、健全な成長のための資金を確保するための一手段に過ぎません。節税それ自体が目的化してしまうと、本質を見失い、かえって企業価値を損ねるリスクがあります。
ここで紹介した5つの視点
-
所得の種類を変える
-
所得の帰属を変える
-
所得の場所を変える
-
所得の時間を変える
-
優遇税制を活用する
これらを活かすためには、「知識」と「計画性」、そして「全体最適」を考える姿勢が不可欠です。
御社の未来のために、ぜひこの5つの視点から節税を見直してみてください。